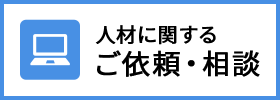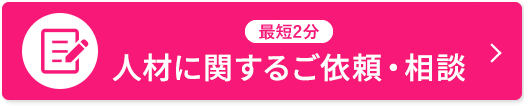よくあるご質問
当社へよく寄せられるご質問を、人材採用のご検討から就業スタート後の労務管理まで、時系列に沿って回答を掲載しております。
派遣に関する制度
- 人材派遣が禁止されている業務はありますか?
- 派遣スタッフを直接雇用の社員にすることはできますか?
- 2015年に派遣法が改正されたと聞きましたが、何が変わったのでしょうか?
- 受け入れ期間にはどのような制限があるのでしょうか?
- 事業所単位の期間制限と個人(組織)単位の期間制限との違いはなんですか?
- 事業所単位の期間制限と派遣スタッフ個人の期間制限の日付が違うのですが、どちらが優先されますか?
- 個人単位の派遣の受入期間制限が超えても、部署が変われば引き続き受け入れられますか?
- 事業所抵触日通知とはなんですか?
- 待遇に関する情報提供通知とはなんですか?
- 派遣受入期間制限の起算日と抵触日はどのように記載したらよいですか?
- 事業所抵触日通知で記載する「雇用保険適用事業所名称」とはなんですか?
- 事業所抵触日通知および待遇に関する情報提供通知は契約更新の都度の提供が必要ですか?
- 契約内容に変更はないのですが、事業所抵触日通知および待遇に関する情報提供通知は提供する必要がありますか?
- 事業所抵触日の延長のための意見聴取とは、何を行えばよいですか?
- 政令業務や自由化業務という区分はどのようなものですか?
- 労働契約申込みみなし制度とは何ですか?
- キャリアアップ措置とは何ですか?
- 自社内で従業員を募集する際に、派遣スタッフにも募集の情報を周知しなければならないと聞きましたが、どのような制度ですか?
- 派遣先企業・派遣労働者・派遣会社(派遣元)の関係はどういうものになりますか?
- 派遣先の「労働基準法」の責任とは、どのようなものでしょうか?
- 離職した労働者を派遣労働者として受け入れる場合は?
- 派遣期間制限の対象外となる派遣スタッフと派遣業務はどのようなものですか?
- 派遣先の雇用努力義務とは?
- 当社社員の教育制度や賃金について、質問がありました。どうしたら良いでしょうか?
- 2020年の派遣法改正では何が変わったのでしょうか?