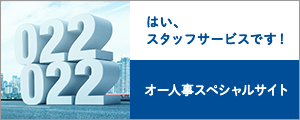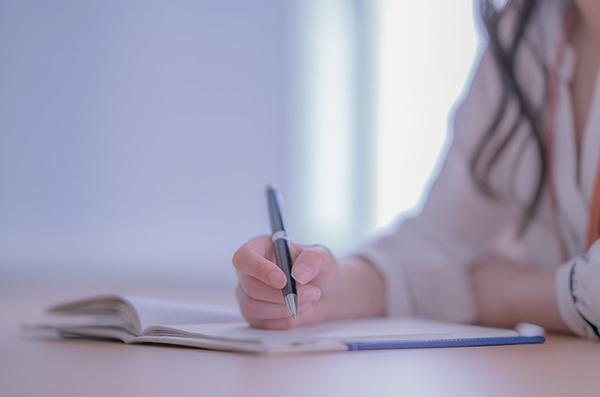人事評価制度とは

人事評価制度は多くの企業で導入されている制度です。人事評価制度は、従業員の貢献度や能力を評価する仕組みで、役職や報酬は、人事評価結果をもとに決められます。
しかし、評価基準が曖昧であったり、評価と報酬が連動していなかったりすることにより、制度がうまく運用できていないケースが存在します。人事評価制度は、わかりやすい基準で等級や報酬と連動させれば、従業員のモチベーション向上にもつながる制度です。
本記事では、人事評価制度の概要やメリット、機能とともに、導入方法や成功させるためのポイントについて解説します。
目次
人事評価制度とは
人事評価制度とは、従業員の貢献度や能力を評価する仕組みです。多くの企業は、人事評価の結果をもとに、役職や報酬を決定します。企業によって評価基準は異なるものの、一般的には以下の3つの要素で構成されています。
|
業績評価 |
・一定期間における会社への貢献度を評価する ・売上や利益、目標達成率が評価の対象となる |
| 能力評価 | ・保有している知識やスキルを評価する ・業務に必要な技能や資格、経験が評価の対象となる |
| 情意評価 | ・仕事に対する姿勢や意欲を評価する ・出退勤状況やルール遵守、仕事に取り組む態度が評価の対象となる |
人事評価制度を導入するメリット
人事評価制度を導入するメリットとして挙げられるのは、以下の3つです。
・ 社内リソース(ヒューマンリソース)の最適化
・ 企業理念やビジョンの浸透
・ 従業員のモチベーション向上
ここでは、それぞれのメリットについて解説します。
社内リソース(ヒューマンリソース)の最適化
人事評価制度を導入するメリットとして挙げられるのは、社内リソースの最適化です。人事評価制度では、評価項目から従業員のスキルや成果を確認できます。評価に基づいて人員を配置すれば、おのずと最適な配置になるのです。
また、評価結果から強化すべきスキルも把握できます。スキルが不足している従業員に対し、研修をはじめとした育成強化もできるでしょう。
企業理念やビジョンの浸透
企業理念やビジョンの浸透も、人事評価制度を導入するメリットに挙げられます。従業員は企業の目標や個人の目標達成に向けて業務に取り組んでいるはずです。
人事評価は企業の目標や個人の目標と連動しており、その目標には企業理念やビジョンが反映されています。そのため、評価項目や基準を示し、それに向かって取り組むことは、自社の理念やビジョン浸透につながるのです。
従業員のモチベーション向上
人事評価制度の導入は、従業員のモチベーション向上にもつながります。人事評価制度により、評価項目が明確になっていれば、従業員がやるべきことも明確になります。評価基準が明確であれば「なぜ給料が上がらないのか」といった従業員の不満が溜まることも少ないはずです。
人事評価制度で、評価項目や評価基準が明確になることにより、従業員の方向性が明確になり、意欲を持って業務に取り組めるのです。
人事評価制度の機能
人事評価制度には、一般的に以下の3つがあります。
・ 等級制度
・ 評価制度
・ 報酬制度
この3つの制度が連動し、人事評価制度が運営されているのが一般的です。例えば、評価制度の結果が良ければ、等級が上がったり報酬が上がったりします。ここでは、それぞれの制度について解説します。
等級制度
等級制度とは、従業員に求める知識やスキル、役割によって職務や職能を階層化した制度です。階層化することにより、従業員は自分に必要な知識やスキルを認識できます。等級制度にも種類があり、主なものとして以下の3つが挙げられます。
| 職能資格制度 | ・勤続年数に応じて階層が上がる ・一度上がった職能は基本的には下がらない |
| 職務等級制度 | ・雇用形態や勤続年数に関係なく、能力に応じて階層が上がる ・階層が下がることもある |
| 役割等級制度 | ・与えられた役割に応じて評価する |
日本の大企業では、職能資格制度が一般的です。ベンチャー企業では、職務等級制度や役割等級制度が導入されています。
評価制度
評価制度とは、従業員のスキルや貢献度を評価する制度です。評価の基準となるのは、企業の行動指標です。一般的に、評価制度の結果が、等級や報酬に反映されます。
評価制度で評価対象となるのは、目標に対する成果や達成度です。ただし、目標には売上や利益のような「定量的な目標」と、提案力や積極性といった「定性的な目標」が存在します。定性的な目標については、主観的な評価になる恐れがあるため、提案回数や発言数といった具体的な目標を設定することが大切です。
報酬制度
報酬制度は、従業員の報酬を決める制度です。報酬には、給与や賞与、退職金があります。表彰や学習機会の提供、休日の付与といった非金銭的なものも報酬のひとつです。
報酬は従業員のモチベーションに大きく影響するため、評価制度との連携やニーズの調査を実施したうえで設計する必要があります。条件や報酬内容を従業員に公表しておけば、よりモチベーション向上につながるでしょう。
人事評価制度を導入する方法

人事評価制度を導入する手順は以下のとおりです。
1. 現状把握と目標設定
2. 評価基準の策定
3. 評価項目の作成
4. 評価方法の作成
5. 導入開始
ここでは、それぞれの手順について解説します。
1.現状把握と目標設定
人事評価制度を導入する前に、現状を把握します。はじめは「従業員のモチベーションが落ちている」「リーダーが育たない」といった漠然としたものでも構いません。漠然とした課題から、どのような従業員がどのような課題を抱えているのかを分析しましょう。
現状を把握したら、企業理念やビジョン、現状把握の結果から企業が従業員に求める「あるべき姿」を設定します。この「あるべき姿」が従業員の目標です。従業員にはさまざまなタイプの人がいることを考えると、あるべき姿は複数設定する必要があります。
ただし、経営層だけであるべき姿を設定した場合、理想が高すぎる姿になるケースがあります。現状把握の結果や従業員へのヒアリングも参考にしたうえで、従業員のあるべき姿を設定しましょう。
2.評価基準の策定
目標設定をしたら、等級制度と照らし合わせ、各階層の評価基準を策定します。「あるべき姿」を達成するための基準を設定することが大切です。各階層に対する役割や行動を具体的にすれば、従業員からの納得感を得られます。
また、同じ等級でも、職種や部門によって評価基準が異なるケースがあります。職種や部門による違いを洗い出し、すり合わせることも大切です。
3.評価項目の作成
評価基準を策定したら、評価項目を作成します。必要な項目は企業によって異なるものの、一般的な項目は以下のとおりです。これらの項目に、自社で必要な項目を追加して運用します。
・ 業績評価:目標達成度/日常業務の成果
・ 能力評価:実務能力/企画力/実行力/改善力/リーダーシップ力
・ 情意評価:規律性/責任感/協調性/積極性
4.評価方法の決定
評価項目を作成したら、評価方法を定めます。評価点の付け方や何段階で評価するかを決めます。多くの企業では、5段階が採用されているものの、3段階評価や7段階評価を採用している企業もあるようです。
ただし、段階が多いと評価に時間がかかったり中央値に点数が寄ってしまったりする傾向があります。そのような傾向を回避するため、4段階を採用している企業もあります。
5.導入開始
評価方法を決めたら、導入スケジュールを決めます。ただし、何の説明もないまま人事評価を導入した場合、現場が混乱する可能性があります。すべての従業員に対し、平等に評価するためには、評価者に対する教育も必要です。
評価実施前に、評価者向けの研修や従業員向けの説明会を実施すると良いでしょう。評価者と従業員が制度を理解したうえで人事評価制度を開始することが大切です。
評価結果を伝える際は、従業員に対するフォローが欠かせません。特に、低評価となった従業員に伝える際は、評価結果に対する客観的な理由や根拠を伝えるとともに、今後の改善点を伝えましょう。従業員任せではなく、組織としてサポートする姿勢を見せることが大切です。
人事評価制度を成功させるには?
人事評価制度を成功させるには、以下のポイントを押さえることが大切です。
・ わかりやすい評価基準にする
・ 定期的に見直す
・ 評価と給与の関係を明確にする
ここでは、それぞれのポイントについて解説します。
わかりやすい評価基準にする
人事評価制度を成功させるポイントには、わかりやすい評価基準にすることが挙げられます。評価基準がわかりにくい場合、従業員はどのように行動すればいいのかわかりません。評価の基準が評価者の主観になっていると感じ、評価結果に不信感を持つ従業員もでてくるでしょう。
従業員に納得感を持ってもらうためには、評価基準に客観性を持たせることが大切です。例えば「目標達成率が100%であれば5段階評価の4とする」のような誰が評価者でも同じ評価結果となるような基準を設ければ、客観性を保てるでしょう。
客観性を保つには、複数人で評価することもひとつの方法です。ひとりで評価した場合、どれだけ公平性を意識しても偏った評価になるケースがあります。複数人で評価することにより、お互いの評価の矛盾や偏りを指摘でき、公平な評価をだせるでしょう。
また、評価項目数についても考慮する必要があります。項目数が多い場合、評価者の負担が大きくなり、業務に支障がでてしまう可能性があります。人事評価制度は、適切な人事評価をすることにより、社内リソースの最適化やモチベーション向上につなげるのが目的のはずです。
スムーズに運用するためにも、手間がかかりすぎない制度にすることを意識しましょう。
定期的に見直す
定期的に見直すことも、人事評価制度を成功させるポイントに挙げられます。企業の状況は、事業拡大や従業員の増減などによって変化します。従業員数の増加によって、これまでの人事評価制度が運用できなくなるケースは珍しくありません。
新しい事業が始まったことにより、求められるスキルがこれまでとは変わることもあるでしょう。また、事業内容や従業員数の変化がなくても、これまでの人事評価制度が完璧というわけでもありません。
事業内容や従業員の変化があったときはもちろん、定期的に運用方法を見直すことが大切です。
評価と給与の関係を明確にする
評価と給与の関係を明確にすることも、人事評価制度を成功させるポイントです。多くの従業員は、人事評価制度を給与が上がる指標として考えています。そのため、評価が高かったにもかかわらず給与が変わらない場合、不満や不信感を持つ可能性があります。
そのようなリスクを回避するためには、人事評価が給与にどのように影響するのかを明確にしておくことが大切です。一般職は20万~24万円、課長は35万~45万円のように、等級や役職ごとに給与幅を設定することや、5段階評価で5をもらえれば等級が上がるといった条件を設定することも良いでしょう。
従業員のモチベーションが上がるような仕組みにすることが大切です。
まとめ

人事評価制度とは、従業員の貢献度や能力を評価する仕組みです。人事評価制度を導入することにより、社内リソースの最適化や企業理念の浸透、従業員のモチベーション向上といったメリットが期待できます。
人事評価制度は、一般的に「等級制度・評価制度・報酬制度」の3つの機能が連動しています。そのため、評価基準や評価項目、評価方法は客観性がありわかりやすいものにすることが大切です。
事業内容や従業員数の変化に合わせて見直しを図ることも必要です。導入方法や成功するためのポイントを理解し、自社に適した人事評価制度を構築しましょう。
《ライタープロフィール》
ライター:田仲ダイ
エンジニアリング会社でマネジメントや人事、採用といった経験を積んだのち、フリーランスのライターとして活動開始。現在はビジネスやメンタルヘルスの分野を中心に、幅広いジャンルで執筆を手掛けている。