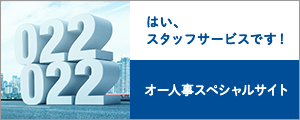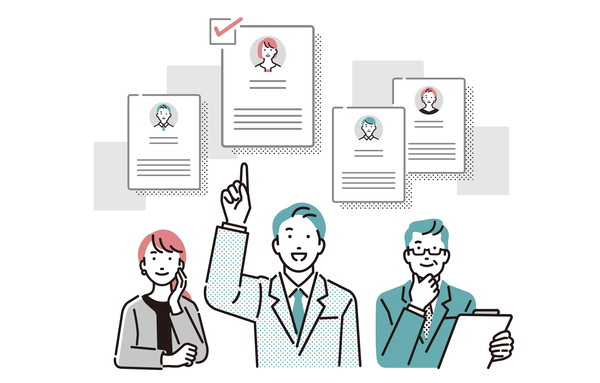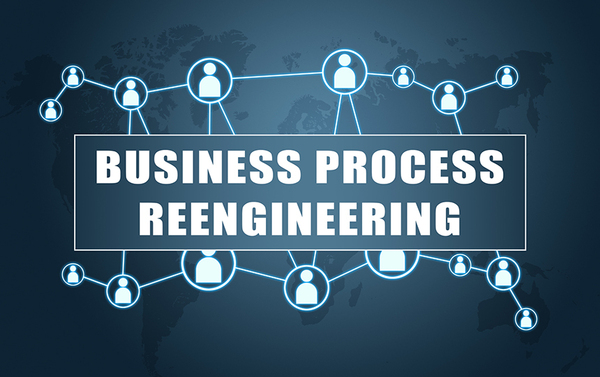
ジョブ型雇用とは?メンバーシップ型との違いは?デメリットは?

従来の日本ではメンバーシップ型雇用を採用している企業がほとんどでした。しかし、近年では、ジョブ型雇用を導入する企業がでてきました。ジョブ型雇用は、職務を限定する雇用形態で、メンバーシップ型雇用では対応できない課題を解決する手段となり得ます。
本記事では、ジョブ型雇用の概要やメンバーシップ型雇用との違いのほか、ジョブ型雇用の導入による企業側と従業員側のメリット・デメリットや導入方法、導入時のポイントについて解説します。
目次
ジョブ型雇用とは
ジョブ型雇用とは、職務内容を限定して人材を採用する雇用形態です。職務定義書(ジョブスクリプション)と呼ばれる書類に職務内容や勤務地、労働時間、待遇などを記載し、合意を得たうえで雇用契約を締結します。
ジョブ型雇用契約を締結した場合、労働者は職務定義書に記載されていない業務をする必要がありません。合理性の高さにより欧米では主流となっている雇用形態ですが、近年では日本でも導入する企業が増えてきました。
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違い
これまでの日本では、人材を採用した後に職務を与える「メンバーシップ型雇用」を導入する企業がほとんどでした。メンバーシップ型雇用は、職務内容や勤務地、労働時間を限定しない雇用形態です。社内の状況に応じて人材を配置するため、異動や転勤もおこなわれます。
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違いは以下のとおりです。
| 項目 | ジョブ型雇用 | メンバーシップ型雇用 |
| 基本原理 | 仕事に人がつく | 人に仕事がつく |
| 採用 | 欠員補充や新業務の 人材確保が中心 |
定期採用が中心 |
| 等級 | 職務等級制度 | 職務資格制度 |
| 昇進 | 成果や実績に合わせて | 勤続年数や年齢に合わせて |
| 降級 | 成果や実績によって実行 | 原則実行されない |
| 賃金 | 職務によって定められる | 勤続年数や年齢によって定められる |
| 育成 | 職務やスキルに応じて 社内外で教育する |
勤続年数や年齢に応じて社内で教育する |
| 雇用保障 | 弱い | 強い |
ジョブ型雇用が日本で注目されている理由
日本では、高度成長期より「新卒一括採用」を採用する企業が多く、今でも主流となっています。しかし、近年では専門性の高い職業が増加したり、適材適所に人材を配置したりする必要性が高まったことにより、ジョブ型雇用に注目が集まっています。
その理由として考えられるのは以下の3つです。
・ 経団連の提言
・ 長時間労働への対応
・ 働き方の多様化
ここでは、それぞれの理由について解説します。
経団連の提言
ジョブ型雇用が注目されている理由として挙げられるのは、経団連(日本経済団体連合会)の提言です。2020年に開催された経営労働政策特別委員会において、国外企業との競争に生き残る対策として、経団連から日本型のメンバーシップ型雇用の見直しとジョブ型雇用の推奨が提言されました。
2022年の経営労働政策特別委員会報告では「ジョブ型雇用の導入や活用の検討が必要」と、さらに踏み込んだ方針を示しています。
経団連の提言により、従来のメンバーシップ型雇用からジョブ型雇用に移行する動きがでてきました。
参考:日本経済団体連合会「2020年版 経営労働政策特別委員会報告 -Society 5.0時代を切り拓くエンゲージメントと価値創造力の向上-」
参考:日本経済団体連合会「2022年版 経営労働政策特別委員会報告-ポストコロナに向けて、労使協働で持続的成長に結びつくSociety 5.0の実現-」
長時間労働への対応
長時間労働への対応も、ジョブ型雇用が注目されている理由に挙げられます。近年では、働き方改革が叫ばれています。その中でも、特に課題となっているのが長時間労働への対応です。
従来のメンバーシップ型雇用の場合、職務が限定されないため、さまざまな業務を兼任する従業員が存在します。その結果、所定の労働時間では業務が終わらず、長時間労働につながるケースがあります。
ジョブ型雇用であれば職務が限定されているため、さまざまな業務を兼任することがありません。ジョブ型雇用は、長時間労働を解決する対策としても注目を集めています。
働き方の多様化
働き方の多様化に対応できることも、ジョブ型雇用が注目されている理由のひとつです。近年では、人口減少に伴う労働人口減少により、多くの企業で優秀な人材の確保が課題となっています。
働き方に対する価値観も多様化してきました。場所や時間にとらわれずに働くことを求める人や、自分の能力を活かせる仕事を求める人、転勤せず同じ場所で働くことを求める人が存在します。
このような状況に対し、従来のメンバーシップ型雇用で優秀な人材を確保することは困難になってきました。メンバーシップ型雇用の特徴である年功序列を前提とした報酬も、上昇志向のある人材にとってはネガティブなイメージに捉えられます。
また、新型コロナウイルスの流行により、テレワークが浸透したことも、ジョブ型雇用に注目が集まる理由です。テレワークでは仕事をしている様子を実際に目にすることができないため、勤務態度を評価することが困難となりました。
ジョブ型雇用であれば、成果で評価できるため、テレワークでの人事評価にも対応できます。働き方の多様化に対応し、優秀な人材を確保することや、テレワークでの公平な人事評価のためにも、ジョブ型雇用の有効性に注目が集まっています。
ジョブ型雇用の導入による企業側のメリット・デメリット

ジョブ型雇用の導入による企業側の主なメリットとして、以下の2つが挙げられます。
・ 即戦力となる人材を採用できる
・ 職務と待遇が連動する
一方、主なデメリットとして挙げられるのは、以下の2つです。
・ 優秀な人材が流出しやすい
・ 異動や転勤などの流動的な配置ができない
ここでは、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。
企業側のメリット①:即戦力となる人材を採用できる
企業側のメリットとして、即戦力となる人材を採用できることが挙げられます。ジョブ型雇用での採用活動では、人材が必要な職種に対し、必要なスキルや経験を持つ人材を募集します。
求職者側も求められているスキルや経験を理解しているため、自社の求めるスキルを持った人材が応募してくるはずです。採用に至った人材は、一定以上のスキルを持っているでしょう。採用後の教育は社内ルールを中心とした最低限のもので済むでしょう。
企業側のメリット②:職務と待遇が連動する
企業側のメリットには、職務と待遇が連動することも挙げられます。ジョブ型雇用は、職務と等級に対して賃金が決まります。メンバーシップ型雇用と異なり、年齢や勤続年数が等級や賃金に影響しません。
そのため、評価を得て等級が上がれば、賃金も上がります。成果と待遇の連動は、評価基準の明確さにもつながります。従業員からの賃金に対する不平不満は少なくなるでしょう。
企業側のデメリット①:優秀な人材が流出しやすい
企業側のデメリットとして挙げられるのは、優秀な人材が流出しやすいことです。前述したとおり、ジョブ型雇用は職務内容が限定されており、職務や等級によって賃金が決まります。
そのため、同じ職務内容でより良い条件の企業があった場合、より良い条件の企業に転職してしまう可能性があります。特に、優秀な人材であれば他社から声がかかることもあるかもしれません。ジョブ型雇用は、人材流出を前提とした雇用形態であることを理解しましょう。
企業側のデメリット②:異動や転勤などの流動的な配置ができない
企業側のデメリットには、異動や転勤などの流動的な配置ができないことも挙げられます。前述したとおり、ジョブ型雇用は職務内容や勤務地が限定されています。原則、職務定義書に記載がない業務は任せられません。
ある部署で人員補充が必要になった場合、メンバーシップ型雇用であれば、他部署から異動させて人員を補充するケースがあります。しかし、ジョブ型雇用で雇用契約を結んだ人材の異動は契約違反です。会社都合での配置変更はできないことを理解しましょう。
ジョブ型雇用の導入による従業員側のメリット・デメリット
ジョブ型雇用の導入による従業員側の主なメリット・デメリットは以下のとおりです。
・ メリット:得意分野で成果をあげやすい
・ デメリット:業務がなくなれば失職する恐れがある
ここでは、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。
従業員側のメリット:得意分野で成果をあげやすい
従業員側のメリットとして、得意分野で成果をあげやすいことが挙げられます。ジョブ型雇用は職務内容が限定されているため、求職者は自分がやりたい業務や保有スキルを活かした業務がある企業を選んで応募できます。
やりたい業務やスキルを活かせる業務であれば、他の業務と比べて成果をあげやすくなることは、想像に難しくありません。得意分野の職務に就けることは、スキルアップの加速や生産性向上にもつながるでしょう。
従業員側のデメリット:業務がなくなれば失職する恐れがある
従業員側のデメリットには、業務がなくなった際に失職する恐れがあることが挙げられます。前述したとおり、ジョブ型雇用で採用した人材は、職務定義書に記載されていない業務を担当できません。
そのため、担当している業務がなくなった場合、担当できる仕事がなくなるため失職する可能性が考えられます。職務内容が限定され異動がない反面、失職のリスクがあることを理解しましょう。
ジョブ型雇用の導入方法
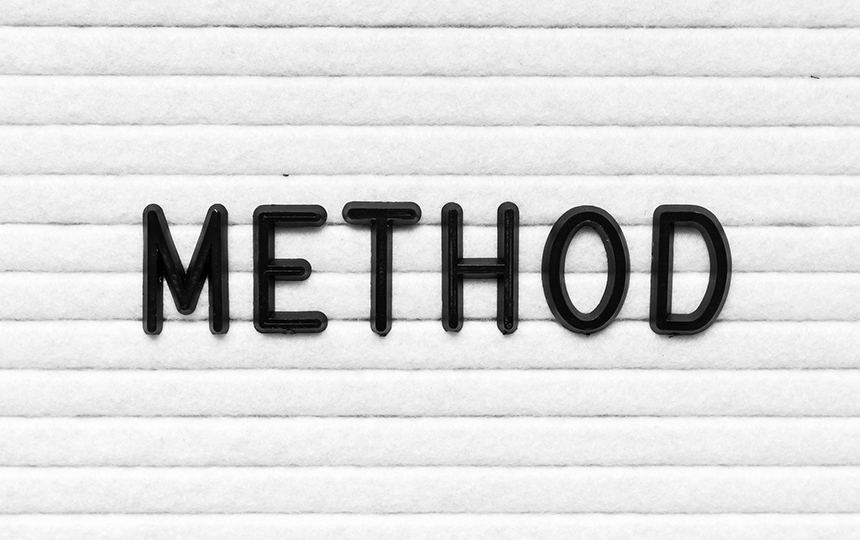
ジョブ型雇用の導入は以下の手順で進めましょう。
1. ジョブ型雇用の適用範囲を検討する
2. 職務定義書を作成する
3. 職務評価をする
4. 等級を設定する
5. 職務定義書や職務レベル定義書を定期的に見直す
ここでは、それぞれの手順について解説します。
ジョブ型雇用の適用範囲を検討する
はじめに、ジョブ型雇用の適用範囲を検討します。メンバーシップ型雇用からすべての職務や役職をジョブ型雇用に切り替えることは得策ではありません。配置変更が頻繁に発生する業務や、ジョブローテーションの対象者からは不満が発生する可能性が考えられます。
自社の職務や役職を分析し、職務レベル定義書を作成したうえで、配置変更が発生しない部署や職務から徐々にジョブ型雇用を進めましょう。
職務定義書を作成する
ジョブ型雇用の適用範囲を決めたら、職務定義書を作成します。職務定義書とは、職務内容や業務範囲、労働条件、必要なスキルをまとめた文書です。ジョブディスクリプションとも呼ばれています。
職務定義書を作成する際は、評価項目や給与体系を見直し、職務に適したものにすることが大切です。職務定義書の項目には、以下のものがあると良いでしょう。
・ 職種
・ 職務名
・ 職務等級
・ 職務の概要や具体的な職務内容
・ 業務範囲や役割
・ 組織における位置付け
・ 責任や権限の範囲
・ 雇用形態
・ 勤務地
・ 勤務時間
・ 必要とされる知識やスキル、資格
・ 待遇
・ 福利厚生
職務評価をする
職務定義書を作成したら、職務評価をします。職務評価とは、職務定義書をもとに職務のレベルを判定するものです。厚生労働省では、職務評価の手法として以下の手法を推奨しています。
|
手法 |
内容 |
|
単純比較法 |
自社の職務を比較し、職務の大きさを評価します。職務を細かく分解するのではなく、全体として捉えたうえで、どちらの職務のほうが大きいのかを比較します。 |
|
分類法 |
作成した職務レベル定義書をもとに職務の大きさを評価します。 |
|
要素比較法 |
職務定義書をもとに、職務の要素を洗い出します。近い要素を持った職務ごとに要素を比較することにより、職務のレベルを評価します。 |
|
要素別点数法 |
要素比較法と同様に、職務を構成する要素別に評価します。職務を比較するのではなく、要素ごとに点数をつけることにより、職務のレベルを評価します。 |
参考:厚生労働省「多様な働き方の実現応援サイト」
等級を設定する
職務評価が終われば、等級を設定します。職務評価で判定した職務レベルをもとに、職務価値を数段階の等級に分けます。等級は人事評価や給与と連動するため、粗すぎてはいけません。ただし、細かすぎる場合、評価に時間がかかるため、適切な等級数を設定しましょう。
等級を区分したら、等級ごとの賃金も設定します。ジョブ型雇用では職務に対する賃金が、労働者のモチベーションを左右する要素です。他社と同じ職務にもかかわらず、賃金が低い場合、他社に転職されてしまう可能性もあります。
人材流出を防ぐためにも、相場に合わせた賃金を設定することが大切です。
職務定義書や職務レベル定義書を定期的に見直す
職務定義書を作成し、等級を設定したら、ジョブ型雇用を導入できます。しかし、職務内容は事業の変化によって変更されるケースがあるでしょう。業務内容に変更があったのにもかかわらず、職務定義書が変更されない場合、形だけのジョブ型雇用になります。
意味のあるジョブ型雇用にするためにも、定期的に職務定義書や職務レベル定義書を見直し、実態に沿った運用をしましょう。
ジョブ型雇用の導入時に注意すべきポイント
ジョブ型雇用の導入時に注意すべきポイントとして、以下の2つが挙げられます。
・ 必要なスキルや条件を求人情報に詳しく掲載する
・ 職務に対する役割や評価基準を伝える
ここでは、それぞれのポイントについて解説します。
必要なスキルや条件を求人情報に詳しく掲載する
ジョブ型雇用の導入時に注意すべきポイントとして、必要なスキルや条件を求人情報に詳しく掲載することが挙げられます。求職者が目にするのは職務定義書ではなく求人情報です。
いくら具体的な職務定義書を作成しても、求人情報にその内容が反映されていなければ、自社が求める人材は応募してきません。自社が求める人材を獲得するためにも、求人情報に募集職種や必要なスキルを詳しく掲載する必要があります。複数の職種を募集する場合は、職種ごとに求人を掲載しましょう。
職務に対する役割や評価基準を伝える
職種に対する役割や評価基準を明確にすることもポイントです。ジョブ型雇用を導入しても、職種ごとの役割を従業員が理解していなければ、ジョブ型雇用は機能しません。
職務定義書を提示するだけではく、職務に対する役割や目標を伝えることが大切です。1度の説明で終わらず、1on1をはじめとした定期面談を通して、継続的に伝えましょう。
まとめ

ジョブ型雇用とは、職務内容を限定して人材を採用する雇用形態です。ジョブ型雇用では、労働者は職務定義書に記載されていない業務をする必要がなく、合理性を求める欧米では主流となっている雇用形態です。
これまでの日本では、メンバーシップ型雇用が一般的でしたが、経団連の提言や働き方の変化により、ジョブ型雇用を導入する企業が増えてきました。ジョブ型雇用には、即戦力となる人材の確保や職務と待遇との連動といったメリットがある反面、人材流出や流動的な配置転換ができないといったデメリットも存在します。
ジョブ型雇用のメリット・デメリットを理解し、自社の事業や職務を分析したうえで、導入を検討しましょう。
《ライタープロフィール》
ライター:田仲ダイ
エンジニアリング会社でマネジメントや人事、採用といった経験を積んだのち、フリーランスのライターとして活動開始。現在はビジネスやメンタルヘルスの分野を中心に、幅広いジャンルで執筆を手掛けている。