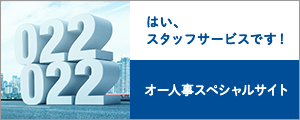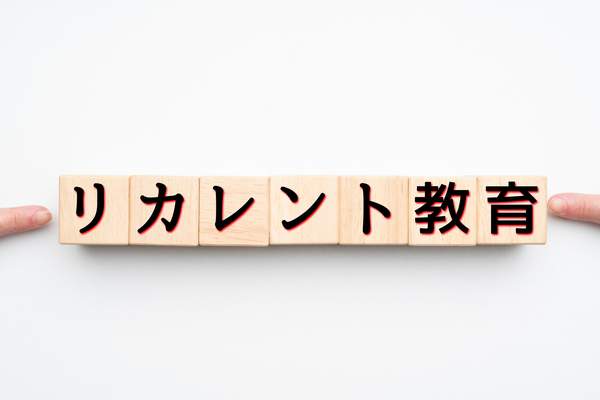MBO(目標管理制度)とは? 意味やメリット、実施手順とOKRとの違いをわかりやすく解説

MBO(目標管理制度)とは、社員が自分で目標を立てる、「経営の神様」ドラッカーが提唱した人材マネジメントの手法です。社員の成長や業績の向上など、さまざまな効果が期待できるため、近年ますます注目を集めています。
本記事では、MBOの意味や注目される背景、種類、メリット・デメリット、実施手順、導入の注意点、よく似た手法のOKRとの違いをわかりやすく説明します。
MBOとは?

MBOとは、Management by Objectives(目標による管理)の略称で、1954年に経営学者のピーター・ドラッカーが提唱した人材マネジメントの手法です。目標による管理とは、「社員の自主的な業務への取り組みを促すための仕組み」を意味しており、日本では「目標管理制度」と呼ばれています。
MBOの特徴は、会社や上司の命令ではなく、社員が自ら目標を決めること。組織の目標達成に向けて自分が貢献できることを「目標」として設定し、自ら行動し、その達成度によって評価を受けます。
MBOは社員が自分で目標を決めるため、個々の自主性を育み、パフォーマンスやモチベーション、生産性の向上、人事評価の効率化、人材育成など、さまざまな効果があるといわれています。
MBOが注目される背景

MBOが日本で広まったのはバブル崩壊後の1990年代でしたが、コロナ禍に見舞われた2020年以降の現在も改めて注目を集めています。その背景には、次のような理由があると考えられています。
・企業が公開すべき情報量の増加に伴い、より厳しい目標達成が求められている
企業に対するディスクロージャー(情報公開)の要求は、年々厳しくなっています。FRS(国際会計基準)が導入されたことで情報公開コストも上昇し、より厳しい目標達成が求められています。
・長期的な事業計画の実行に対応できる組織構成のため
中小企業は適切な後継者がいなければ、事業の継承自体が困難になります。長期的な事業計画の実行に対応できる組織にすることや人材育成を目的として、MBOに注目する企業が増えているようです。
・上場企業の場合は、上場の維持のために厳しい事業運営が求められているため
上場企業は上場を維持するために、よりシビアな事業運営が求められます。社員も常に自ら目標を明確に設定し、それを達成することによって、成果や業績を上げていくことが必要となります。
・目標を持つことで、目標達成に向けた取り組みが促せる
社員が自ら企業の戦略やビジョンに基づいた個人目標を持つことで、目標達成に向けた積極的な取り組みを促すことができます。自己管理に基づくマネジメントをすることで社員の成長も期待できるでしょう。
・MBOを繰り返すことで継続的な改善につながる
MBOは、社員が自ら目標を設定し、PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を繰り返し実行していきます。MBOを実施することで、継続的な業務改善につながることが期待されています。
MBOの種類

MBOは、その目的によって3種類に分類されています。3つのタイプのMBOを同時におこなっている企業もあれば、1つの目的に特化している企業もあります。それぞれの特徴を見てみましょう。
・組織活性型
目的は、組織を活性化することです。社員に自ら目標を設定させることで、一人ひとりの自発的な行動を促進します。社員の意思を尊重し、成長を促すことで、組織やチームの活性化を目指します。
・人事評価型
目的は、人事評価を効率化することです。目標の達成度、それに向けた取り組みなど、MBOにおける成果と行動を人事評価に反映させます。組織活性型と併せて実施している企業も多くあります。
・課題達成型
目的は、企業としての目標達成や課題解決。それらに基づいて個人の目標設定をするMBOです。年間売り上げなど全社目標を部門目標に分け、さらにチーム目標へと細分化、個々の目標へと落とし込みます。
MBOのメリット

日本では、約8割の企業がMBOを導入しているといわれています。なぜそれほど多くの企業がMBOを導入しているのでしょうか。代表的な5つのメリットを見てみましょう。
・組織の目標と方向性を統一できる
企業が業績を伸ばすためには、組織と社員一人ひとりが同じ方向を向くことが重要です。MBOは、社員が自ら組織目標に基づいた個人目標を立てるため、会社や部門、チームなどの目標と、個々の目標を統一できるメリットがあります。
・自己管理のスキルが高まる
目標管理には、「目標と自己統制によるマネジメント」という意味があります。MBOは、上司の命令ではなく、社員が自ら目標を決める自己統制に基づく制度です。そのため自身の行動を律し、スキル向上や業務効率化を目指す、セルフマネジメント(自己管理)のスキルが高まるといわれています。
・業務へのモチベーションが高まる
人は、命令や報酬といった外発的な動機だけでは、高いモチベーションを保つことができないといわれています。MBOは社員が自ら目標を考え、自発的に行動するため「やらされ感」が軽減します。MBOは内発的動機が高まりやすく、業務へのモチベーションアップ効果が高いといわれています。
・人材育成につながる
MBOは人材育成につながります。組織目標に基づいた個人目標を考え、目標達成に向けた計画を立案するのは管理職の業務であることが一般的です。MBOでは、すべての社員が自分でおこなうため、非管理職であってもマネジメントの基礎を身につけることができます。目標達成に向けた問題分析や業務改善なども必要となるため、将来のマネージャー候補も育成しやすくなるといわれています。
・人事評価がしやすくなる
人事評価型のMBOは、目標の達成度や、そのプロセスによって評価を決めるのが一般的です。MBOを評価基準に反映すると人事評価がしやすくなります。達成できたこと・できなかったことが明確になるため、フィードバックもしやすく、部下も自身の改善点が理解しやすくなるといわれています。
MBOのデメリット

MBOはさまざまなメリットが期待できるといわれていますが、デメリットも指摘されています。MBOの導入を検討している企業の方は、以下のポイントも参考にしてみてください。
・達成基準を明確にしにくい職種もある
MBOの難点は、目標設定の難しさです。総務や人事など、成果を数値化しにくい職種もあり、「〇〇を周知徹底する」「〇〇を効率化する」といった曖昧な目標を設定すると、部下は「達成した」と思っても、上司は「達成していない」と判断し、低評価を受けた社員が不満を持つおそれがあります。
成果を数値で表しにくい職種についても、「組織サーベイを半期に一度おこなう」「給与計算日を中3日に短縮する」など、達成基準はできるだけ定量数字で置くようにすることをおすすめします。
・各社員で自由な目標を設定できない
MBOの意味や目的が正しく理解されていない場合や、会社の理念やビジョンが社員に浸透していない場合は、目標を自由に設定できないことに対して社員のモチベーションが下がることが考えられます。
MBOは社員が自ら目標を決める制度ですが、自由に目標を設定できるわけではありません。「企業の目標を達成するため、社員は自分が貢献できることを個人目標にする」=「組織と個人が共通する目標を持つ」。MBO導入の際は、まずはこの意識を周知徹底することが大事なポイントとなります。
・目標達成を強く意識すると、低い目標を設定しがち
人事評価型のMBOは、目標達成における成果や行動を処遇に反映できるメリットがあります。しかし、目標達成を強く意識するあまり、社員が低い目標を設定しがちになるデメリットも指摘されています。
また、達成不可能な高すぎる目標を設定して達成できない場合、給与ダウンなどによって社員のモチベーションが下がる可能性もあります。達成可能でありながら、成長も促す適切な難易度の目標を見極めて部下にアドバイスする。これが上司の重要な役割となります。
・協調性が失われ、チーム力が低下する場合がある
MBOは、個人の成果だけを目標にしてしまうと協調性が失われ、チーム力が低下する場合があります。上司が自身の成果だけに腐心し、部下やメンバーの面倒を見なくなるおそれもあります。
MBOの本来の目的は組織力を強化すること。チームとしての目標も設定する、動機づけや進捗管理、人材育成など、マネジメントにおける目標も設定するなど、目標設定の仕方には注意が必要です。
MBOの実施手順

MBOの失敗を防ぎ適切に運用するためには、どうしたらいいのでしょうか。MBOを導入する際は、次のような手順を踏むことをおすすめします。
STEP1:企業の理念や利益に沿った目標を設定する
MBOの最大の目的は、企業としての目標を達成すること。MBO説明会や目標設定研修、管理職研修などを実施し、制度の趣旨や会社の理念、組織目標などを伝え、理解を得たうえで、各社員に自身の目標設定をしてもらいましょう。理念や利益に沿った目標になっているか、達成可能で自身が成長できる目標になっているかなど、部下の目標を上司が確認し、必要であれば修正を促します。
STEP2:目標達成までの計画を決める
目標設定ができたら目標達成までの計画を練ります。無理なく目標達成ができる計画を立て、目標達成を疎外するリスクも想定して、プランB・プランCといった別の計画も用意しましょう。期日から逆算して計画を策定し、Excelやスプレッドシート、専用ツールなどで目標管理シートを作成します。
STEP3:目標達成までの計画を実行する
目標と計画ができたら、実行に移します。目標管理シートで期日までの時間や達成度を確認しながら実行し、障害や難度が上がりすぎている部分があれば、上司と相談して計画を修正します。達成が遅れているメンバーがいたら相互に助け合い、チームの総合力で目標達成できる風土を作りましょう。
STEP4:目標達成の状況を上司と振り返り、評価する
目標の期日になったら、達成状況についての振り返りをします。部下と上司で目標達成に至るまでの成果と行動を共有し、部下による自己評価、上司による客観的評価とフィードバックをおこないます。達成できたことは褒め、不足していたことは指摘し、数字だけでなくプロセスについても評価することが重要です。MBOは、振り返りを繰り返していくことで効果が高まるといわれています。
MBO導入の注意点

MBOは、社員の成長や生産性の向上が期待できる優れた制度です。しかし、運用方法を誤ってしまうと効果が発揮されない場合も少なくありません。MBO導入の注意点を確認しておきましょう。
・モチベーションが高まるような目標を設定する
MBOは、個々の能力や成長度に応じた達成可能な目標に設定することが大切ですが、低すぎる目標では社員のモチベーションが上がらず、成長も期待できません。目標は達成できる確率が50%の難易度にするなど、モチベーションアップにつながるような目標に設定することを意識しましょう。
・目標の達成基準を明確にする
MBOは、目標の達成基準を明確にすることが重要です。数値化しにくい職種もありますが、「効率化を徹底する」「ミスをなくすよう努力する」といった達成基準が曖昧な目標では、「達成できたのか、できなかったのか」客観的な判断ができません。達成基準はできるだけ定量数字で表し、「納期を中3日から2日に短縮する」「ミスを5個から3個に減らす」など、測定可能な目標に設定しましょう。
・上司が部下に目標を押しつけない
MBOは、社員が自ら目標を決めることが重要です。上司が部下に目標を押しつけてしまうと単なるノルマになってしまい、MBOの効果が発揮されません。上司の役割は、組織の目標を伝える、部下の目標を承認する、あるいは軌道修正を促すこと。そして進捗を管理し、結果に対して適切なフィードバックをおこなうことです。管理職に対する教育・育成が、MBOを成功させる鍵といわれています。
・成果だけでなくプロセスも評価の対象にする
MBOは、社員の成長も重要な目的の1つ。目標達成は大事ですが、成果だけでなくプロセスも評価の対象にしましょう。成果だけを評価すると個人プレーに走りやすく、チームワークが低下するおそれがあります。成果は運にも左右されますが、行動は再現性があります。目標達成に向けた行動をできるだけ具体的に計画し、実行できた行動を評価することによって今後の成長が期待できるでしょう。
MBOとKPIの違いとは
MBOとよく似た用語として、KPIがあります。MBOとどのような違いがあるのでしょうか。
KPIとはKey Performance Indicatorの略で、重要業績評価指標の意味があります。
KGI (Key Performance Indicator)といわれる「重要目標達成指標」を達成するために、それに至るまでの最適な過程を洗い出し、その過程をどのくらいの状態で通過すればいいのかを、可視化して計測するために、この「KPI」はあります。
つまり「KGI」は「最終的なゴール(結果)」を知る指標であり、 「KPI」はそのゴールにたどり着くまでの「プロセス」が適切かどうかを知る指標といえるでしょう。
では、「KPI」と「MBO」ではどんな違いがあるのでしょうか。「目的」や「レビュー」などの観点で比較してみましょう。
「目的」の観点でいえば、「KPI」はプロジェクトの最終目標の数値で計測し、具体的な達成度合いをチェックし評価します。主にプロジェクトマネジメントに活用されています。一方「MBO」は、先の説明にもあるように、個人の評価、さらにその先にある個々の報酬を決定するために用いられることが多いです。
「レビュー」頻度においても、「KPI」と「MBO」で違いがあるようです。「KPI」を運用するには、毎日~毎月、高い頻度で定期的にモニタリングが行われています。かたや「MBO」は、個人の評価(査定)に活用されることが多いため、半年~1年ペースで実施されています。「KPI」と「MBO」では、このような違いが見られます。
MBOとOKRの違い

OKRとは、MBOとよく似た人材マネジメントの手法です。正式名称は「Objectives and Key Result(目標と成果指標)」。OKRはMBOから派生した目標管理の一種で、社員やチームのパフォーマンスを向上させることに特化した手法です。MBRとOKRの違いについても確認しておきましょう。
・制度の目的
どちらも制度の目的は、組織と個人の目標を共通化することです。
MBOは組織における個人の役割を明確にし、各社員の自主性を引き出します。組織への貢献度を評価し、人事評価に反映します。
OKRは難易度の高い目標に挑ませることによって、社員やチームのパフォーマンスの飛躍的な向上をはかります。そのため人事評価には反映しないのが一般的で、MBOと併用している会社も多くあります。
・個人目標の共有の範囲
個人目標の共有の範囲も異なります。
MBOは、個人目標を上司と部下で共有します。目標設定会議などを通じて評価者である上司同士でも共有し、人事評価や人材育成の指標として使用します。
OKRは、個人目標を組織全員で共有するのが一般的です。組織の目標と成果指標を全社員に周知するため、社員間のコミュニケーションが活性化しやすくなるメリットがあるといわれています。
・評価の頻度
評価の頻度も異なります。
MBOは、年度単位か半期単位(1年または6ヶ月に1回)で評価をおこなうのが一般的です。
OKRは企業によって異なりますが、4半期単位(3ヶ月ごと)に評価をおこなう企業が多いようです。スピーディーな目標設定と測定をすることによって、めまぐるしく変化するグローバル市場にも対応しやすくなっており、インテルやGoogleなどが導入したことでも有名です。
・評価の計測方法
MBOは、評価の測定方法に一般的な決まりはなく、企業によって異なります。
OKRは、測定しやすいように目標を数値化し、客観的なデータによって測定するのが一般的です。
・理想とされる目標の達成度
MBOは、達成可能な目標(達成できる確率が50%の難易度など)を設定するため、100%の達成率が理想とされます。
OKRは、あえて難易度の高い目標を設定するため、60~70%の達成率が理想とされています。達成率が常に100%の場合は、もっと野心的な目標を立てることが必要となるでしょう。
まとめ
〈ライタープロフィール〉
鈴木にこ/ライター
求人メディアの編集者を経て、フリーランスとして活動中。派遣・新卒・転職メディアの編集協力、ビジネス・ライフスタイル関連の書籍や記事のライティングをおこなう。
〈編集〉
西谷 忠和
新卒・中途採用、進学などのメディアにて広告制作ディレクターを経験後、2007年に独立。現在は、フリーのライターとして採用サイト、求人メディアの広告、採用のオウンドメディア、人材サービス企業のインナーコミュニケーションなどのコンテンツ制作に携わっています。またライフワークとして、20~50代のビジネスパーソンやフリーランスのキャリア支援を行うキャリアコンサルタントとしても活動中。