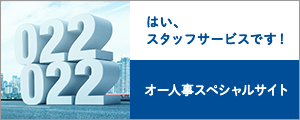職場環境の改善による効果とアイデアを紹介

働き方改革とともに「職場環境改善」が注目されています。たとえば、適切な温度・湿度の管理をおこなう、疲れた時に身体を横にすることのできる休憩室等を設置するなど、職場を疲労やストレスを感じることの少ない快適なものとすることは、事業活動の活性化にも良い影響を及ぼします。
今回は、職場環境についての解説と改善することで得られる効果、改善のためのアイデアをご紹介します。
目次
そもそも職場環境とは?

職場環境とは、照明や温度といった室内環境、仕事量や仕事のしやすさなど仕事の負荷や自由度、上司や部署内での人間関係など、労働者を取り巻く環境のことをいいます。
たとえば、空調が強過ぎて体調を崩す、集中して業務に取り組みたい社員がいる一方で雑談が聞こえてくるなど、職場環境が悪い、または快適でなかった場合、体調不良やストレスの原因になるかもしれません。そればかりか、集中力が散漫となり、生産性の低下につながる可能性もあります。企業として職場環境の改善は、労働者を守るために欠かせない取り組みといえます。
職場環境に対しての配慮義務
労働契約法 第5条(労働者の安全への配慮)では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めています。安全への配慮とは、健康診断や労働時間管理をしっかりして労働者の健康に配慮する「健康配慮義務」「ハラスメント対策」、そして「職場環境配慮義務」も含まれます。
事業者に対して求められている快適な職場環境形成のための措置
また、労働安全衛生法第3条においては、事業者に対して、快適な職場環境形成のための措置として4つの指針が示されています(同法第71条3項)。
|
1.作業環境の管理 |
2020年4月には健康増進法が改正され、大人数が利用する施設においての喫煙を禁止されたことを受け、企業の禁煙に向けた動きが増加すると見込まれています。昨今のテレワークの増加により、職場環境についての意識が希薄になりがちですが、テレワーク環境と併せて職場環境見直しの検討が必要といえそうです。
ストレスチェック
2015年2月より労働安全衛生法の改正により、労働者が常時50名以上の全事業者(法人・個人)において、ストレスチェックの実施を義務化しています。また、厚生労働省の第13次労働災害防止計画(計画期間:2018年度~2022年度)によると、「ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上にする」ことが目標として掲げられています。
《参考サイト》
厚生労働省|職場環境改善ツール
https://kokoro.mhlw.go.jp/manual/
職場環境の改善や整備が必要な理由
毎日働く職場環境は整っているべきだけれど、改善・整備の必要がある理由はあまり理解できていないという方のために、職場環境の改善・整備が必要な理由を紹介します。
可能な限り多くの労働者が快適に働ける職場だと感じてもらえるように、各項目をセルフチェックしてみてはいかがでしょうか。
労働者の安全や衛生の確保
労働者が安心・安全に、そして衛生的に働ける設備、環境が整っていることは一人ひとりのパフォーマンス最大化にも役立ちます。
たとえば、下記のような環境では仕事以外に気にしなければならないことが多く、パフォーマンス低下につながる可能性があります。
・建付けが悪くドアの開閉が困難など、安全に働けない
・ハラスメントがある職場のため安心して働けない
・ゴミ捨てや清掃が定期的に行われず、衛生的ではなくストレスが溜まる
自分自身が上記環境で心地よく働けるかどうかを想像してみると、職場環境が社員のパフォーマンスに大きく関わることを理解できます。
広義には人間関係等のストレスへの対策
先に挙げた例のような職場環境の場合、そこで働く人には毎日少なからずストレスが溜まっていきます。ストレスが溜まると別の問題が勃発しかねません。
職場環境を改善・整備することで日々のストレスをなくし、社員が快適に集中できる環境となり、パフォーマンスの最大化につながります。
労働条件に問題を抱えている場合の改善
労働時間が長い、休日出勤があるなど労働条件に問題がある場合も、環境の整備が必要です。以下のような状態になっている場合は、即刻原因を突き止め、職場環境の改善・整備が必要です。
・出席する必要性が薄い会議が多く、その影響で労働時間が長引いている
・業務フローが改善されず、休日出勤を余儀なくされている
職場環境というと物理的な環境だけに思えますが、人間関係などのストレスや労働状況も職場環境に含まれます。「働きづらさを抱えている人がいないか」という観点で職場環境をチェックすると、改善すべきポイントが見えてくるでしょう。
職場環境の要素
「オフィスはキレイ、整理整頓もできていて衛生的にも問題ない」そんな風に思っていても、その他の職場環境要素を見逃していて人材が定着しない、退職者が増加するなどの問題が起こることもあります。
職場環境というと、つい物理的な環境を思い浮かべがちですが、その他にどんな要素が含まれるのかを改めて解説します。
オフィスなどの作業環境
まず、オフィスなどの作業環境という物理的な側面です。ツールの充足度合い・通信環境・部屋の明るさ・物の整理整頓度合い・清掃状況・音・匂い・温度湿度など、五感で感じるものがすべて清潔で快適に過ごせる状態かどうかが挙げられます。
作業をする際に障害となりそうな事柄がないかを、確認するようにしましょう。
職場の人間関係
物理的なもの以外の要素には、人間関係が含まれます。職場の人間関係がギスギスしていると相談しづらい、話しかけづらい、仕事を依頼しにくいなど、業務がうまく進まなくなる要因が生み出されます。
こうした職場環境で働いていると、働き続けたくないと感じるようになったり、仕事を一人で進めようとしたりするなど事業や業務を進めるうえでの問題が起きるようになります。それがさらに別の社員のストレスを生み出す可能性もあるため、大きくなる前の対処が必要です。
担当する業務の内容
担当する業務の内容も、職場環境に含まれます。たとえば「プロジェクトでAさんだけに負担がかかりすぎている」という状態、「仕事の自由度や裁量権が適切に割り振られておらず、偏りが生じている」なども職場環境に関係してきます。
その人材に合った量と責任の仕事が割り振られているか、役割分担が適切な状態にあるかも職場環境改善・整備の一貫として見ておく必要があるでしょう。
職場環境を改善するとどんな効果がある?

職場環境を改善することで、さまざまな効果が期待されます。いくつか紹介します。
ストレスを軽減することで業務に集中できる
厚生労働省が公表した「令和2年度 労働安全衛生調査(実態調査)」によると、54.2%の労働者が仕事で強いストレスを感じていることがわかりました。そのなかでも、強いストレスの内容として上位に挙げられているのが「仕事の量」(42.5%)、「仕事の失敗、責任の発生等」(35.0%)、「仕事の質」(30.9%)、対人関係(セクハラ・パワハラを含む)(27.0%)でした。
このような労働者が職場で感じているストレスを、職場環境の改善によって軽減することができたら、心身の不調の改善につながるでしょう。職場にいる時間が快適であれば、労働者も業務に集中できるようになりでしょう。
人間関係の改善
近年、さまざまな企業では部署の枠を超えた社員同士のコミュニケーションを増やそうと、固定の席を設けず、社員が好きな席で作業ができる「フリーアドレス」を導入する企業が増加しています。フリーアドレスはコミュニケーション促進に有効であるほか、自由に席を選べることから対人トラブルがあった相手と距離を置くこともできます。
また、些細な悩みを上司に相談できる場として、個人面談やチャットツールなどを導入することも良好な職場環境を実現するために必要です。
作業効率の向上
職場環境改善の取り組みは、生産性の向上にも効果があります。
従業員がいきいきして活気ある職場は、社員のパフォーマンスや生産性も高まり、結果として会社の利益向上につながるでしょう。
離職率の減少
職場環境が適したものでなければ、労働者が業務に対してモチベーションを維持できず、結果として離職を選択することも考えられます。少子高齢化により、今後ますます人材の確保が重要となるからこそ、人材の流出を食い止めるための職場環境改善の取り組みは必須といえるでしょう。
職場環境改善のアイデア

職場環境改善のためのヒント集より、職場環境の改善につながるアイデアを一部ご紹介します。
作業計画の参加と情報の共有
■個人あたりの過大な作業量があれば見直す
特定のチーム、または特定の個人あたりの作業量が過大になる場合があるかどうかを点検して、必要な改善をおこなう。
■各自の分担作業を達成感あるものにする
分担範囲の拡大や多能化などにより、単調な作業ではなく個人の技量を生かした達成感が得られる作業にする。
勤務時間と作業編成
■労働時間の目標値を定め残業の恒常化をなくす
1日、1週、1ヶ月ごとの労働時間に目標値を設け、ノー残業デーなどを運用することなどで、長時間労働が当たり前である状態を避ける。
■繁盛期やピーク時の作業方法を改善する
繁盛記やピーク時などの特定時期に個人やチームに作業が集中せず作業の負荷や配分を公平に扱えるように、人員の見直しや業務量の調整をおこなう。
■個人の生活条件に合わせて勤務調整ができるようにする
個人の生活条件やニーズに応じて、チーム編成や勤務条件などが柔軟に調整できるようにする。(例:教育研修、学校、介護、育児)
円滑な作業手順
■個人ごとの作業場所を仕事しやすくする
作業台の配置、肘の高さでの作業、パソコン操作方法の改善など、各自の作業場のレイアウト、姿勢、操作方法を改善して仕事しやすくする。
■作業の指示や表示内容をわかりやすくする
作業のための指示内容や情報が作業中いつでも容易に入手し確認できるようにする。(例:見やすい指示書、表示・ラベルの色分け、標識の活用など)
■作業ミス防止策を多面に講じる
作業者が安心して作業できるように作業ミスや事故を防ぎ、もし起こしても重大な結果に至らないように対策を講じる。(例:作業手順の標準化、マニュアルの作成、チェック方法の見直し、安全装置、警報など)
作業場環境

■温熱環境や音環境,視環境を快適化する
冷暖房設備などの空調環境、照明などの視環境を整え、うるさい音環境などを個々の作業者にとって快適なものにする。
■衛生設備と休養設備を改善する
快適で衛生的なトイレや更衣室を確保して、ゆっくりとくつろげる休憩場所、飲料設備、食事場所や福利厚生施設を備える。
職場内の相互支援
■上司に相談しやすい環境を整備する
従業員が必要な時に上司や責任者に問題点を報告、また相談しやすいように普段から職場環境を整えておくようにする。(例:上司に相談する機会を確保する、サブリーダーの設置、相談しやすいよう職場のレイアウトを工夫するなど)
■チームワークづくりをすすめる
グループ同士でお互いを理解し支えあい相互に助け合う雰囲気が生まれるように、メンバーで懇親の場を設けたり、研修の機会を持ったりするなどの工夫をする。
■仕事に対する適切な評価を受け取ることができる
作業者が自分の仕事のできや能力についての評価を、実績に基づいて納得できる形でタイミングよく受け取ることができるようにする。
安心できる職場のしくみ
■個人の健康や職場内の健康問題について相談できる窓口を設置する
心の健康や悩みやストレス、職場内の人間関係などについて気兼ねなく相談できる窓口、または体制を確保する。
■セルフケアについて学ぶ機会を設ける
セルフケア(自己健康管理)に役立つ情報を提供し、研修を実施する。
(例:ストレスへの気づき、保健指導、ストレスへの上手な対処法など)
■昇進・昇格、資格取得の機会を明確にしてチャンスを公平に確保する
昇進・昇格のモデル例やキャリア開発のための資格取得機会の有無や時期が明確にされ、また従業員に公平にチャンスが与えられることが従業員に伝えられているようにする
《参考サイト》
・厚生労働省:職場環境改善のためのヒント集
(メンタルヘルスアクションチェックリスト)
https://kokoro.mhlw.go.jp/manual/files/manual-file_01.pdf
このヒント集は、職場従業員の参加のもと、仕事の負担やストレスを減らして、快適に安心して働くための職場環境に関する改善アイデアが盛り込まれています。これらのヒントは、職場のメンタルヘルスやストレス対策のためにすでにおこなわれ、役立っている改善事例を日本全国から集めて、全部で6つの領域、30項目に分類してチェックリストとしてまとめられたものです。
このほか、下記3種類の「職場の改善マニュアル」のダウンロードが可能です。
・ヒント集を用いた職場環境等の改善マニュアル
・メンタルヘルスアクショントレーナーの手引き
・職場環境改善のためのヒント集項目一覧表
まとめ
職場環境は快適だと思う基準が労働者によってそれぞれ異なります。事業者にとって、誰もが納得できる職場環境を整えることは困難かもしれませんが、労働者が気持ちよく健康に働けるような職場環境があれば、業務効率の向上や離職率の低下といった成果を得られるのも事実です。
職場環境改善のヒントは、実際に働く社員の声から聞くほかありません。まずはアンケートで率直な意見を募りつつ、限られたコストや時間のなかで少しでも良い職場環境にできるよう取り組むところから始めてみてはいかがでしょうか。職場環境の改善は、事業者と労働者の双方にメリットがありますので、自社の課題を把握と改善をおこなうことでより良い職場づくりをおこないましょう。
《ライタープロフィール》
ライター:ナカイマミ(編集者・ライター)
求人媒体で求人広告の制作、編集記事の制作に10年以上携わった後、女性誌、生活情報誌、地域活性に関係する媒体などで多くの取材、ライティングを手掛ける。気が付けば、47都道府県を踏破。海外よりも日本が好き。
編集:高下 真美(ライター)
新卒で人材派遣、人材紹介企業に入社し、人事・総務・営業・コーディネーターに従事。その後株式会社リクルートジョブズ(現・株式会社リクルート)に転職し、営業として8年勤務後、HR系ライターとしてフリーランスへ転身。現在は派遣・人材紹介・人事系メディアでの執筆、企業の採用ホームページの取材・執筆の他、企業の人事・営業コンサルタントとして活動中。