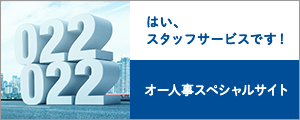育児介護休業法の制度や改正ポイント、取得可能日数について解説

「育児介護休業法ってどのような制度?」「育児休業や介護休業は誰でもとれるの?」「最近の改正で何が変わったのか知りたい」といったお悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
かつては、育児や介護を理由として離職する人が少なくありませんでしたが、近年は仕事と育児や介護が両立できるよう法改正が進められています。
しかし、労働者であれば誰でも育児休業や介護休業を取得できるというわけではありません。
そこで本記事では以下のポイントについて解説します。
・ 育児介護休業法の概要
・ 2022年の育児介護休業法の主な改正ポイント
・ 育児介護休業法の主な制度
・ 企業が導入するメリット
・ 導入する企業側の対応
法改正によって、男性も育児休業が取りやすくなりました。
本記事を読むことで、育児介護休業法の改正ポイントや企業が今後取り組むべき課題について理解を深められます。最後まで読んで、ぜひ働きやすい職場づくりの参考にしてください。
目次
育児介護休業法とは
育児介護休業法は、子どもや親といった法律で決められた対象者の育児や看護、介護をするために、休みを取得できる制度です。労働者が育児や家族の介護を理由として仕事を辞めることなく、仕事と両立ができるようサポートするために定められました。
育児介護休業法の第一条では、労働者の福祉の増進にとどまらず、経済及び社会の発展に資することが目的であると掲げられています。労働者の退職を防止することで、人材不足の解消と会社の発展につながり、ひいては経済や社会の好循環にもつながることをねらいとしたものです。
育児介護休業法の主な改正ポイント

2022年の育児介護休業法の改正によって、従来より休業が取得しやすくなりました。ここでは、改正の主なポイントについてまとめています。
雇用環境整備の義務化
2022年4月の法改正によって、事業主には、育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関して以下のいずれかの措置への取り組みが求められるようになりました。
これらの職場環境を整備することで、育児休業の取得を促進するという目的があります。
・ 研修の実施
・ 相談体制の整備
・ 自社の取得実例の収集・提供
・ 育児休業を促すための方針の周知
妊娠・出産等を申し出た労働者への個別周知・意向確認の義務化
同じく2022年4月から、事業主には労働者本人または配偶者が妊娠・出産等を申し出た場合に、育児休業制度に関して個別の周知と意向確認をおこなうことが求められています。
| 周知事項 | 個別周知と意向確認の手段 |
| ・ 育児休業・産後パパ育休の制度や申し出先 ・ 育児休業給付に関すること ・ 育児休業・産後パパ育休中の社会保険料の取り扱い |
・ 面談 ・ 書面 ・ FAX ・ 電子メール等 |
この際、取得を控えさせるような、労働者に不利益となる周知や意向確認は認められません。
有期雇用労働者に対する育児・介護休業取得要件の緩和
従来、有期雇用労働者が育児休業を取得するためには、以下の2つの条件を満たす必要がありました。
(1)引き続き雇用された期間が1年以上である
(2)子が1歳6ヶ月になるまでに雇用契約(更新される場合には、更新後の契約)が満了し、更新されないことが明らかでないこと
しかし、2022年4月の改正によって、上記(2)の条件のみとなり無期雇用労働者と同じ扱いとなっています。
産後パパ育休の創設
2022年10月から、出生時育児休業(産後パパ育休)が新たに創設されました。産後パパ育休とは、出生後8週間の間に休業を4週間(28日)まで取得できる制度で、通常の育児休業とは別に2回に分割して取得が可能です。
育児休業の分割取得
育児休業は、原則として子が1歳(最長2歳)になるまで取得が可能です。従来は育児休業の分割はできませんでしたが、2022年10月の改正により、分割して2回の取得が可能になりました。
育児休業取得状況の公表義務化
2023年4月から、従業員数が1000人を超える企業に対し、育児休業等の取得状況の公表が義務化されました。これにより、対象企業は年に1回、自社ホームページや「両立支援のひろば」のWebサイト上で、男性の育児休業等と育児休業目的休暇の取得率を公表しなければなりません。
育児介護休業法の主な制度
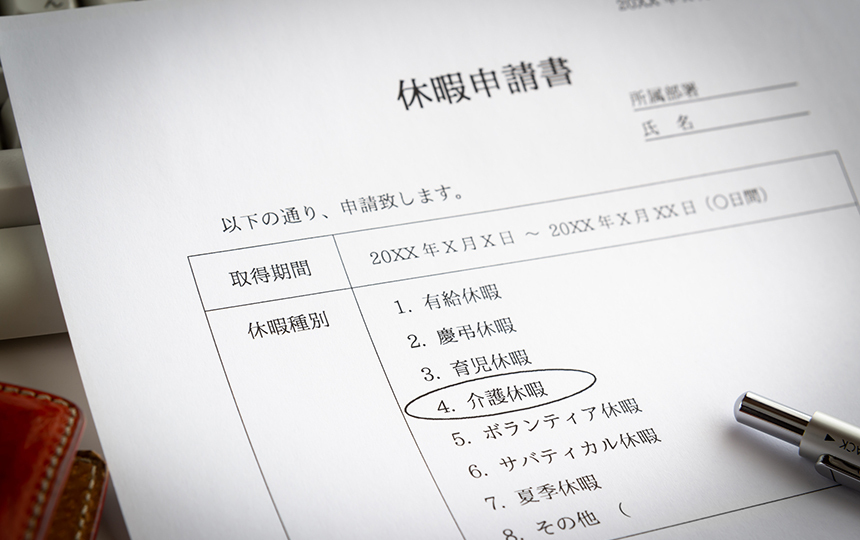
育児介護休業法には主に次の5つの制度があります。
・ 育児休業
・ 出生時育児休業(産後パパ育休)
・ 子の看護休暇
・ 介護休業
・ 介護休暇
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
育児休業
育児休業は、原則として1歳未満の子を養育するための休業です。育児休業を取得することは、労働者の権利です。
労働契約によって使用者には賃金支払いの義務、労働者には会社のために働く義務が生じますが、労働者が育児休業を申し出ると労働義務は消滅します。会社に育児休業に関する規定がなくても、労働者の休業申し出を拒めません。
育児休業は原則として、子が1歳に達する日までの期間とされています。
ただし、子が保育所等に入所できないなどの理由がある場合には1歳6ヶ月まで(再延長の場合は2歳まで)の期間、延長して休業が可能です。
有期雇用労働者は、前章の法改正の要件緩和にともない、育児休業を申し出た時点で子が1歳半になるまでに労働契約が期間満了となり、更新されないことが明らかでない場合に育児休業を取得できます。
注意点として、日雇労働者や所定労働日数が週2日以下の者などの労使協定によって除外された一定の労働者は、育児休業の対象となりません。
出生時育児休業(産後パパ育休)
出生時育児休業は通称「産後パパ育休」とも呼ばれ、出産直後の休業取得のニーズが高い時期に、従来の育児休業よりも柔軟に取得できるよう設けられた制度です。
出生時育児休業が取得できるのは、原則として生後8週間以内の子を養育し産後休業を取得していない男女の労働者です。産後8週間の産後休業期間中の労働者は取得できないため、出生時育児休業の主な対象は男性とされています。
通常の育児休業と同様に、日雇労働者や労使協定によって対象外となっている一定の労働者は除かれます。
また、有期雇用労働者は、子の出産予定日または出生日のいずれか遅い日から起算して8週間経過日の翌日から6か月経過するまでに労働契約が期間満了となり、更新されないことが明らかでない場合に出生時育児休業が取得できます。
子の看護休暇
小学校就学前の子を養育している労働者は、事業主に申し出ることで子の看護休暇を取得できます。子の病気やけがだけでなく、予防接種や健康診断を受けさせる目的でも取得が可能です。限度日数について、会社によって特別な定めがない場合は、4月1日から3月31日までの年度で考えます。
| 子の人数 | 子の看護休暇の限度日数 |
| 1人 | 年5日 |
| 2人以上 | 年10日 |
子の看護休暇は、1日や半日単位だけでなく時間単位でも取得が可能です。従来は1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できませんでしたが、2021年の法改正によって全ての労働者が取得できるようになりました。
ただし、子の看護休暇を時間単位で取得するのが困難な業務に従事している労働者については、労使協定の締結によって時間単位の休暇制度の対象から除外されています。
介護休業
介護休業は、労働者が要介護状態の対象家族を介護するために取得する休業です。
ここで述べる「要介護状態」というのは、「負傷、疾病、または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」ことを指しています。
介護休業の利用期間は、対象家族1人につき3回・通算93日までです。3回まで分割取得できるというのが、他の制度にない特徴となっています。
対象家族とは、以下の者をいいます。
1. 配偶者(事実婚を含む)
2. 父母
3. 子
4. 配偶者の父母
5. 祖父母
6. 兄弟姉妹
7. 孫
日雇労働者は、介護休業の対象外です。
また、有期雇用労働者は、介護休業の申し出時点で介護休業を取得する予定日から起算して93日が経過する日から6か月経過する日までに雇用契約が期間満了し、更新されないことが明らかでないことが求められます。
その他に労使協定の締結によって、入社1年未満の者や申し出から93日以内に雇用契約が終了することが明らかな者、週の所定労働日数が2日以下の者が対象外となります。
介護休暇
介護休暇は、労働者が要介護状態の対象家族の介護や世話をするために休暇を取得できる制度です。対象家族の通院の付き添いや介護サービスの手続き代行といったケースにも利用が可能となっています。介護休暇の「要介護状態」や「対象家族」は、前述の介護休業と同じです。
取得できる限度日数はこちらです。
| 対象家族の人数 | 介護休暇の限度日数 |
| 1人 | 年5日 |
| 2人以上 | 年10日 |
対象家族の範囲は、介護休業と同じです。2021年 からは、時間単位でも介護休暇が取得できるようになりました。
介護休暇についても、日雇労働者は対象にはなりません。また、入社後6か月未満の労働者や週の所定労働日数が2日以下の労働者は、労使協定の締結によって対象外となります。
企業が育児介護休業を導入するメリット

育児介護休業制度の導入は、企業にさまざまなメリットをもたらします。
最新の「令和4年度雇用均等基本調査(厚労省)」 によると、男性の育児休業取得者の割合は17.13%(前年度13.97%)と、上昇傾向にあるものの依然として低い数値となっています。
人員不足などの影響で、導入がなかなか進まないという企業の実態がうかがえる数字です。
子育てや介護と仕事との両立を目的とする育児介護休業法ですが、ここでは、制度を導入することにより、考えられるメリットを挙げていきます。
従業員のモチベーションアップ
家庭の事情で休まなければならないときに、適切な休みを取得できるというのは、従業員へ大きな安心感を与えます。心理的に安心して仕事に取り組むことができると、仕事へのモチベーションも上がります。従業員のモチベーションアップは、離職の防止にも効果的です。
企業の信頼度向上
2023年の法改正により、従業員数1000人を超える企業には、育児休業等の取得状況の公表が義務づけられています。自社の取得状況が、他社と比較されることは避けられません。
取得率が高い場合は、企業としてのイメージアップや信頼度の向上につながると言えるでしょう。
業務の標準化による業務効率の向上
育児介護休業の取得が促進されると、業務フローの見直しや業務の標準化といった効率化が図られます。これは、休業によって生じる人員不足を補うために必然の流れです。もともとの目的は育児介護休業の取得推進ですが、結果として業務効率の向上につながることは、企業にとって大きなメリットです。
企業側に求められる対応
労働者が安心して休業や休暇を取得するためには、企業側の対応も大切です。企業に求められる対応について、具体的にみていきましょう。
環境の整備
職場によっては休業や休暇が取りにくいところもあるでしょう。
特に男性の育休の取得率は、女性に比べて低いのが現状です。男性の育児休業の取得を促進するために、企業には雇用環境の整備が求められます。そのためには、事業主が積極的に育児休業を促すPRをしたり、社内に相談窓口を設置したりするなどの施策が有効です。
休業取得前後の対応
労働者が休業を取得する前後の対応も大切です。労働者から休業の申し出があると、職場内外での調整が必要になります。社内の他の部署から代替要員を確保したり、臨時に人を雇ったりする必要があるかもしれません。休業中の会社の業務に支障が出ないように、早めの対応が大切です。
従業員への理解増進
育児や介護のための休業に対して、従業員に理解してもらうことも大切です。育児休業などの取得率を高めるためには、休業しやすい職場風土を醸成する必要があります。
そのためには、従業員に育児休業などに関する研修を実施したり、休業の取得率を上げるために会社が取り組む方針などを周知したりすることが重要です。また、休業等を申し出た本人に対しては、制度や休業中の社会保険料の扱いなどについての説明が必要です。
各ハラスメントへの対策
その他に企業に求められているのが、休業等を申し出た労働者に対するハラスメント対策です。
例えば、産後パパ育休の取得を申し出た労働者に対して「男のくせに育休を取るな」と言ったり、育児休業を申し出た女性に対して「長期間休まれたら迷惑だ」と言ったりすることはハラスメントに該当します。事業主には、上司や同僚からのこうしたハラスメントを防止する措置を講じる必要があります。
一般的に知られている用語として、妊婦に対するマタニティハラスメント(マタハラ)がありますが、その他にも、育児休業等を取得しようとする男性従業員へのパタニティハラスメント(パタハラ)や介護休業を取得しようとする従業員へのケアハラスメント(ケアハラ)といったものが挙げられます。
まとめ
育児・介護休業法は、育児や介護と仕事の両立を目的とした制度です。出産した女性の約8割が育児休業を取得するなど、出産しても子育てと仕事の両立を希望する人が多いなか、企業としてはいち早く制度を導入することが求められます。
本法に則って、就業規則の改定や職場環境の整備などを推し進めることは、労働者だけでなく、企業にとってもメリットがあるという認識が重要です。
〈執筆監修者プロフィール〉
西本 結喜(監修兼ライター)
一般企業の人事職8年目。金融業界や製造業界を経験し、業界ごとの慣習や社風の違いを目の当たりにしてきた。現場で得た知識を深めたいと社会保険労務士試験に挑戦し、令和元年度合格。現在は小売業の人事職に従事しながら、独立開業に向けた準備を進めている。
【参考】
育児・介護休業法について、出生時育児休業(パパ育休)について
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000076_20230401_503AC0000000063
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
介護休業について
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/holiday/index.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/closed/index.html
法改正のポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/001245931.pdf
有期雇用契約者の育児休業改正について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r01_12_27.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/
「令和4年度雇用均等基本調査(厚労省)」(令和4年度の男性育休取得率の部分)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r04/07.pdf
「ハラスメントについて」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137179.pdf