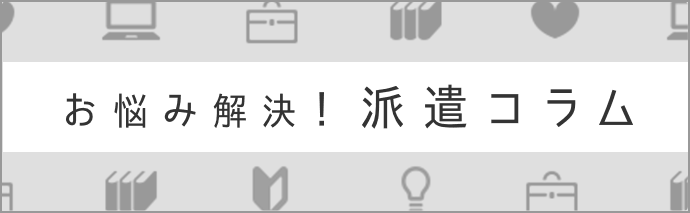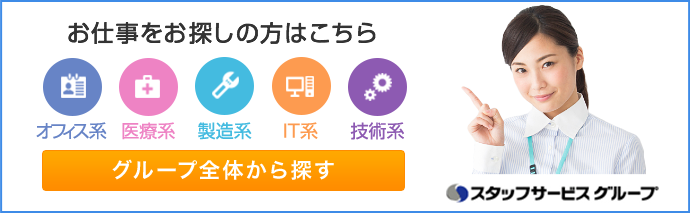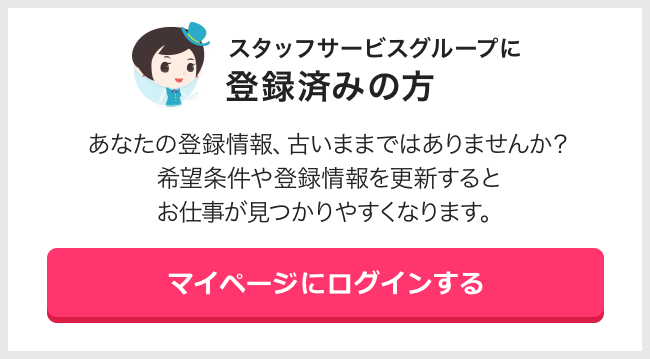扶養控除とは?年収ごとの控除金額や配偶者控除との違いについて解説

「年◯◯万円以上働いたら扶養から外れてしまう」「夫の扶養内で働きたい」など、扶養控除についての声を耳にする機会は少なくありません。扶養控除とは、法律で定められた要件を満たす親族を扶養している人が、所得税や住民税を一定の割合で軽減できる所得控除制度です。
混同しやすい配偶者控除や配偶者特別控除との違いや、社会保険上の扶養との違いなどとともに詳しく解説していきます。扶養控除について知りたい方は、最後まで読んでぜひ参考にしてください。
目次
扶養控除とは
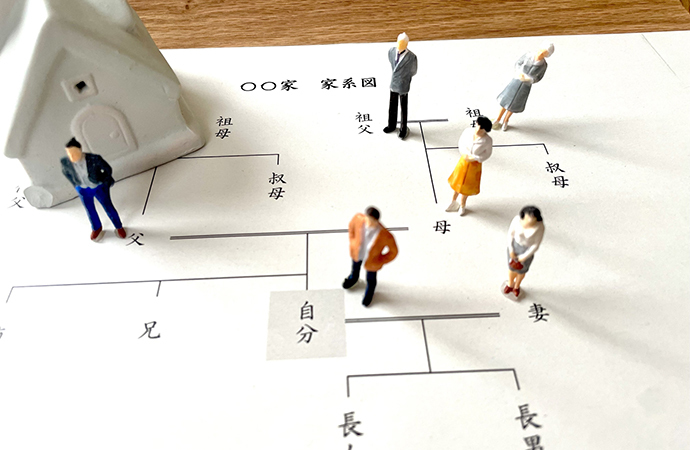
扶養控除とは、16歳以上の子どもや親など、扶養控除の対象となる親族を養っている場合に受けられる制度で、医療費控除や社会保険料控除などの数ある所得控除のうちの一つです。
要件に該当する扶養親族がいる場合に適用され、その親族の年齢や同居の有無等によって控除額が異なります。
扶養控除の目的は、納税者の税負担を軽減することです。養っている親族がいる場合とそうでない場合では、経済的な負担が大きく異なります。このような納税者の事情を考慮し、扶養している人数に応じて、家計を支える扶養者の負担を軽くしているのです。
税法上の扶養控除、社会保険上の扶養の違い

一概に「扶養」といっても、税法上と社会保険上では内容が大きく異なります。本章では、両者の違いを説明していきます。
税法上の扶養とは
税法上の扶養とは、前述のとおり、扶養する家族がいる場合に納税者の所得税や住民税が控除される制度を指します。
税法上の扶養に入って控除を受けられると、納税者(=扶養者)の税負担が軽減でき、扶養に入った被扶養者自身の所得税や住民税も免除または減額されます。
ここで述べる「扶養」とは、納税者が配偶者や子ども、親などを経済的に支えることです。
税法上の扶養に入るには、被扶養者の年収が103万円以下(合計所得48万円+給与所得控除55万円)という条件があり、103万円を超えると対象外となります。
ただし、扶養控除の対象とされる「扶養親族」に配偶者は含まれていません。配偶者に関わる控除は、扶養控除とは別に「配偶者控除」「配偶者特別控除」という制度が設けられており、これらの控除は上記の扶養控除とは別のものです。
「配偶者控除」「配偶者特別控除」については後ほど詳しく解説します。
社会保険上の扶養とは
社会保険上の扶養とは、会社員や公務員である主たる生計者(扶養者)の社会保険の被扶養者になることです。扶養者の社会保険に加入することで、被扶養者は社会保険料(健康保険料・厚生年金)を納める必要がなくなります。
社会保険上の扶養に入るためには、被扶養者の年収が130万円未満であることが必要です。
配偶者控除・配偶者特別控除との違い
扶養控除というと配偶者も該当すると考えられがちですが、前述のとおり、配偶者は扶養控除の対象ではありません。配偶者を扶養している場合には、一定の要件を満たすと「配偶者控除」「配偶者特別控除」が適用されます。
つまり、一般的に述べる扶養控除と配偶者控除・配偶者特別控除との主な違いは、「扶養する親族が配偶者かそれ以外の親族か」という点です。
また、配偶者控除・配偶者特別控除の場合は、納税者の収入が1,000万円以下であることが適用の要件ですが、扶養控除の場合は納税者本人の所得制限はありません。さらに、扶養控除は人数の制限もないため、要件に該当すれば全て控除の対象となります。
配偶者控除と配偶者特別控除の適用条件について見ていきましょう。
配偶者控除の適用条件
配偶者控除を受けるには、次の条件を満たす必要があります。
1. 納税者本人の1年間の合計所得金額が1,000万円以下
2. 配偶者が12月31日時点で以下の4つの要件をすべて満たす
2.1. 民法規定による配偶者である(内縁関係は対象外)
2.2. 納税者本人と生計を一にしている
2.3. 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入がある場合103万円以下)
2.4. 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払を受けていない
あるいは白色申告者の事業専従者でない
年間の合計所得金額が48万円以下など、扶養控除と同様の条件も複数あります。
配偶者特別控除の適用条件
配偶者に48万円を超える所得があると配偶者控除の適用ができなくなりますが、年収が133万円以下の場合は配偶者特別控除を受けられます。配偶者特別控除の適用条件は、以下のとおりです。
1. 納税者本人の1年間の合計所得金額が1,000万円以下
2. 配偶者が12月31日時点で以下の5つの要件をすべて満たす
2.1. 民法規定による配偶者であること(内縁関係は対象外)
2.2. 納税者本人と生計を一にしていること
2.3. 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下
2.4. 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払を受けていない
あるいは白色申告者の事業専従者でない
3. 配偶者自身が配偶者特別控除を適用していないこと
4. 配偶者が「給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載された「源泉控除対象配偶者がある居住者」として源泉徴収されていない
5. 配偶者が「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載された「源泉控除対象配偶者がある居住者」として源泉徴収されていない
配偶者特別控除は、夫婦間でお互いに控除を受けることはできません。それぞれが配偶者特別控除の要件を満たしていたとしても、いずれかの納税者のみ控除が適用されます。
扶養控除の対象

扶養控除の対象となる親族(控除対象扶養親族)は、次の5つの条件を全て満たしている人をいいます。
1. 控除を受ける年の12月31日時点で16歳以上
2. 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)
3. 納税者と生計を一にしている
4. 年間の合計所得金額が48万円以下
5. 青色事業専従者として給与を受けていない、または白色申告者の事業専従でない
それぞれについて、以下で詳しく解説します。
1. 控除を受ける年の12月31日時点で16歳以上
その年の12月31日時点で16歳未満の親族は、控除対象扶養親族には該当しません。15歳以下の子供を扶養している場合、扶養控除ではなく「児童手当」の対象となります。この手当が受給される代わりに、16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外となっています。
2. 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)
「血族」は納税者本人の親族、「姻族」は納税者本人の配偶者の親族のことです。例えば、納税者本人の両親や子どもは1親等、兄弟姉妹などは2親等にあたり、扶養控除では、対象の親族が幅広く認められています。
3. 納税者と生計を一にしている
「生計を一にする」とは、必ずしも同居や生活費の共有を要件としているわけではありません。例えば、単身赴任や病気療養のための別居、親元を離れて暮らす学生、地方に住んでいる両親を扶養する場合、生活費や学資金、療養費などの送金がおこなわれていれば「生計を一にする」とみなされます。
4. 年間の合計所得金額が48万円以下
収入があっても合計所得金額が48万円以下であれば、扶養控除の対象となります。所得金額とは、年間収入から給与所得控除などを差し引いた金額を指します。
アルバイトやパート労働者など給与所得のみの場合は、年収103万円以下であれば該当します。ただし、給与所得以外にも所得がある場合は、それらの合計所得が48万円以下でなければなりません。
5. 青色事業専従者として給与を受け取っていない、または白色申告者の事業専従でない
青色事業専従者とは、青色申告の個人事業主のもとで働き、給与収入を得ている家族のことを指します。例えば、同居する弟が青色申告事業者である父親の事業を手伝い、青色事業専従者給与を受け取っている場合、弟は扶養控除の対象外となります。
個人事業主の確定申告の際に、事業専従者への給与の一部を「専従者控除」として所得控除できることから、「専従者控除」と「扶養控除」の二重適用ができないような仕組みになっているのです
なお、個人事業主のうち白色申告者の事業専従者は、給与収入の有無に関係なく扶養控除の対象から外れる点に注意しましょう。
扶養控除は扶養親族の年齢により種類が異なる
扶養控除の控除額は、扶養親族の年齢によって異なります。ここでは「控除対象扶養親族」「特定扶養親族」「老人扶養親族」について説明します。
控除対象扶養親族
「控除対象扶養親族」とは、次に説明する「特定扶養親族」や「老人扶養親族」に該当しない人を指し、「一般の控除対象扶養親族」とも言われます。具体的には、16歳以上18歳以下、23歳以上70歳未満の控除対象扶養親族であれば、これに該当します。
一般の控除対象扶養親族の控除額は、38万円です。
特定扶養親族
控除を受ける年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の場合、「特定扶養親族」に該当します。特定扶養親族は63万円の控除を受けられ、一般の控除額(38万円)よりも多くなっています。
この年齢に該当する子どもを養っている場合、教育費などの経済的負担が大きくかかっていると考慮され、他の区分よりも優遇された控除額となっています。
老人扶養親族
「老人扶養親族」とは、70歳以上の控除対象扶養親族を指します。老人扶養親族の控除額は、同居の有無で異なります。同居していなければ48万円、同居していれば58万円の控除を受けられます。
なお、病気の治療を目的に1年以上の長期入院をしている場合は、「同居」と取り扱って問題ないとされています。ただし、老人ホームなどの施設に入所している場合は、「同居」とみなされないため注意が必要です。
社会保険上の扶養について

本章では社会保険上の扶養について詳しく解説していきます。法改正により、社会保険加入の対象が広がるなど情勢の変化が早いため、気になる方はこまめに確認しましょう。
扶養者の社会保険に被扶養者が入ること
社会保険上の扶養とは、主たる生計者(扶養者)と同じ社会保険に加入し被扶養者になることを言います。社会保険では扶養者のことを「被保険者」と呼びます。
社会保険上の扶養は、被扶養者になると、自身で社会保険料を負担しなくても健康保険や年金制度に加入できる仕組みです。
社会保険料を負担しなくてよいというメリットはありますが、デメリットも存在します。
例えば、健康保険において被扶養者は一部の給付が対象外であるほか、年金においては、国民年金のみの加入(第3号被保険者に該当し、厚生年金には加入できない)になるなど、扶養者と被扶養者の保障が全く同じということではありません。
社会保険上の扶養となる条件は以下です。
・被保険者と認定対象者(被扶養者になろうとする人)が同一世帯に属している場合
認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上または一定の障害を有する場合は180万円未満)かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること
・被保険者と認定対象者が同一世帯に属していない場合
認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上または一定の障害を有する場合は180万円未満)かつ、被保険者からの援助による収入額より少ないこと
なお、社会保険上の扶養は、税法上の扶養とは対象範囲が異なります。
具体的には、被保険者に生計を維持されている人のうち、被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹です。これらの親族については、同居の有無は問われません。しかし被保険者と三親等以内の親族を被扶養者とする場合は、同居し家計を一にしていることが求められます。
直近の法改正
2022年10月の法改正内容
社会保険の改正として、被保険者になる=社会保険に加入する条件が変わったことが挙げられます。以下の5つの条件を満たすと、配偶者の扶養に入ることを希望していても、自らが社会保険に加入しなければなりません。
● 週の所定労働時間が20時間以上
● 雇用期間が継続して2ヵ月超見込まれること
● 賃金が月額8万8000円以上(年106万円以上)
● 学生ではないこと
● 勤務先の従業員数が101人以上(2024年10月からは51人以上)
このうち、「勤務先の従業員数が101人以上」という部分について、2022年9月までは「501人以上」が条件でした。つまり、2022年を境にこれまでより社会保険の加入を義務とされる人が増え、パートやアルバイトといった非正規雇用の働き方でも、扶養から外れ自身で社会保険に加入する人が多くなりました。
2024年10月の法改正内容
前述の勤務先の人数について、2024年10月にさらなる法改正が予定されています。この改正により「101人以上」という条件が、「51人以上」となることが発表されています。これまでより小規模の事業所でも、従業員への社会保険の加入が義務付けられることになり、厚生労働省の発表によると2024年の改正では約70万人が加入義務化の対象になるということです。
被扶養者の年収の壁について
「年収の壁」とは、給与の手取り額が減らないようにと意識されている年収の基準を指しています。「年収の壁」は一般的に103万円、106万円、130万円、150万円の4つが挙げられます。
これまで出てきた「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」では、扶養に入る要件も異なっており、その要件が「年収の壁」に関係しています。
103万円の壁
「103万円の壁」は税法上の扶養の話にあたり、パートやアルバイトで働く人に所得税の納税義務が発生するかどうかのボーダーラインのことです。年収103万円を超えてしまうと、越えた分に対して所得税が徴収されます。
106万円の壁
「106万の壁」は、自身で社会保険に加入する必要が出てくる年収の目安の一つです。
これは前述のとおり、2022年の法改正により、従業員が101人以上の事業所で働く場合、年収106万円を超えると社会保険の加入対象とされたためで、パートやアルバイトとして働く被扶養者であっても、以下の要件に当てはまると扶養から外れて社会保険料を自ら負担しなければなりません。
なお、2022年の改正では従業員101人以上の事業所が対象でしたが、2024年10月からは51人以上となる予定のため、106万円の壁の対象者がさらに増えることになります。
130万円の壁
年収130万円は、社会保険の被扶養者となる条件のひとつです。「106万の壁」の要件に該当しなくとも、この金額を超えれば社会保険の扶養からは外れます。
この場合、自身の勤務先の社会保険に加入する、または勤務先の加入条件に該当しなければ、国民健康保険や国民年金に加入します。
ただし、繁忙期による一時的な収入増加など一定の条件に当てはまる場合は、年収130万円を超えても、最大2年間被扶養者の資格が認められる措置が取られています。
この措置が認められるためには、『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書 』という書類に勤務先の証明が必要です。
150万の壁
「150万円の壁」は税法上の扶養の話です。配偶者特別控除を満額受けられる年収が150万円となっています。年収が150万円を超えると控除額が段階的に引き下げられる仕組みで、配偶者の年収201万円以上になると控除額は0円になります。
扶養控除の申請方法

扶養控除の申請方法には、「年末調整」と「確定申告」の2パターンあります。それぞれの手続きについて、確認していきましょう。
年末調整での申請方法
会社員など給与所得者が扶養控除を受けるためには、年末調整での申請が可能です。年末調整で手続きをする場合は、「扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出します。
その際は「控除対象扶養親族」の欄に、名前、続柄、マイナンバー(個人番号)、その親族の所得見積額、住所などを記入します。
勤務先から「扶養控除等(異動)申告書」などの年末調整のための書類が配布されたら、自身の世帯状況に応じて必要事項を記入したうえで、忘れないように提出しましょう。
なお、年間の給与総額が2,000万円以上の場合や中途退職者で再就職の予定がある場合や2カ所以上から給与を受け取っていて、自社以外の勤務先で「扶養控除等(移動)申告書」を提出している場合は、年末調整の対象ではありません。その場合は、自身で確定申告の手続きをする必要があります。
確定申告での申請方法
給与所得者に該当しない個人事業主や、年末調整の対象外となる会社員などは、確定申告にて扶養控除の申請をおこないます。
具体的には、申告書第二表の「扶養控除」の欄に対象扶養親族の名前、マイナンバー(個人番号)、続柄、生年月日を記入します。扶養控除額の合計額を申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」の扶養控除欄に記入します。
確定申告の受付期間は、原則として毎年2月16日~3月15日です。忘れないように税務署へ提出しましょう。
まとめ
「扶養控除」などの単語は知っているものの、詳しくは分からないという人も少なくありません。近年、社会保険の適用範囲が段階的に拡大されていることもあり、「扶養」や「◯◯万円の壁」というワードを見聞きすることが増えています。税法上の扶養控除や社会保険上の扶養などを正しく理解することは、自身や家族の働き方や今後のライフプランを考えるうえでも重要です。ご自身の状況に照らし合わせて、参考にしてください。
執筆監修者プロフィール
西本 結喜(監修兼ライター)
一般企業の人事職8年目。金融業界や製造業界を経験し、業界ごとの慣習や社風の違いを目の当たりにしてきた。現場で得た知識を深めたいと社会保険労務士試験に挑戦し、令和元年度合格。現在は小売業の人事職に従事しながら、独立開業に向けた準備を進めている。
【参考】
・扶養控除全般(制度概要・控除区分・対象者):
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
・「生計を一にする」の定義
国税庁 https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/cat2/cat22/cat22b/cid067.html
・青色専業専従者給与と専業専従者控除
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
・配偶者控除
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
・配偶者特別控除
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
・社会保険上の扶養・法改正(適用範囲拡大)
厚生労働省厚生年金ガイドブックhttps://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi.pdf
・103万円の壁
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800.htm
・150万円の壁
国税庁 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/pdf/01.pdf
・社会保険上の扶養「2024年の法改正により約70万人に加入義務化の影響」
厚労省「年金制度の仕組みと考え方第9被用者保険の適用拡大」P6 2つある図のうち、下の図より
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000955316.pdf
・年末調整の対象となる人
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
・確定申告書の記載方法
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/03/3_01.htm