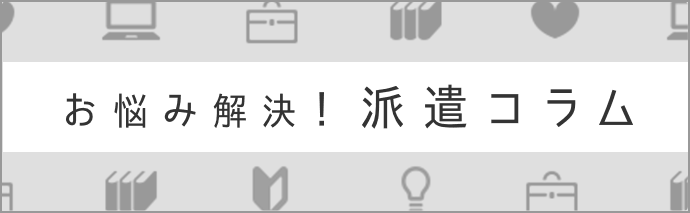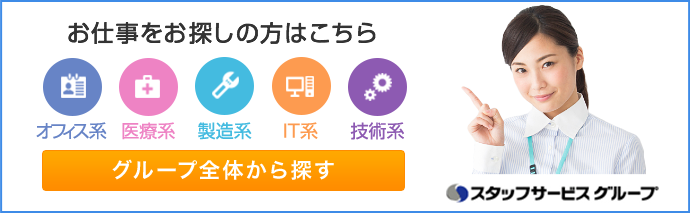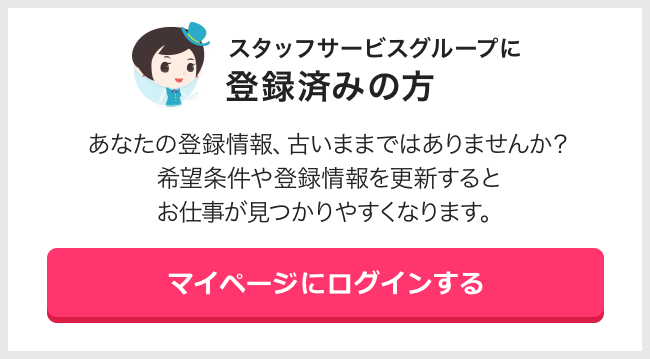質問力とは?

職場における質問力の有無は、仕事内容の理解度やプロジェクトの進度に差がつき、大きな影響を及ぼすものです。「周囲とうまく仕事を進めている人ほど、的を射た質問をしている」と実感した経験がある方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、質問力を磨くメリットや質問力を磨くポイントをまとめて紹介します。仕事ができる人と思ってもらうためにも、この記事を参考に質問力を身につけられるようチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
目次
質問力とは?

質問力とは、距離感やシーンを見誤らないよう気をつけながら、目的の内容を短い時間で聞き出せる能力のことです。あなたの職場にも「ちょうどそれ聞きたかった」と感じるような質問を、代表して聞いてくれている人はいませんか?
そういう方が質問力を持っている人です。
仕事を進める際は、その仕事の目的や到達すべきゴールの明確化、不明点や疑問点を解消するために質問をします。
質問に答えてもらうためには、内容によって質問の仕方を工夫する必要があります。
質問の種類
質問の仕方は、下記2パターンに分けられます。
・オープンクエスチョン
オープンクエスチョンとは、「はい・いいえ」などで答えられない、考えて回答する必要のある質問を指します。例えば、下記のような質問がオープンクエスチョンです。
「この企画を実施した際、何が実現できればゴールといえますか」
「◯◯さんの意見を聞かせてもらえますか」
考えて答えなければならない質問のため、相手に負荷をかける種類の質問方法です。そのため、会議の最初などにこの質問をしてしまうと、会議のリズムが悪くなり、進行を妨げる可能性があります。また、移動中など落ち着いて話せない状況でこうした質問をすると、「忙しいから考える余裕がないのに状況が読めない人だ」などと、思われる可能性があります。
オープンクエスチョンは、時間があるとき、一対一でじっくり話せるタイミングなどを狙って質問するようにしましょう。
・クローズドクエスチョン
クローズドクエスチョンは、「はい・いいえ」で答えられる質問です。
「この商材を売ったことはありますか」
「A社との打ち合わせ日程は決まっていますか」
事実を答えるだけで良いため、相手に負荷が少ない種類の質問方法です。最初にクローズドクエスチョンをいくつかして、答えやすい雰囲気になってきたタイミングでオープンクエスチョンをするなど、組み合わせて使うといいでしょう。
オープンクエスチョンは、相手に負荷を与える質問ではあるものの、真意を捉えるには最適な手法です。反対にクローズドクエスチョンは連続すると誘導しているような印象を与えますが、要点を絞り込んでいくのに適しています。
オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンをうまく織り交ぜることを心がけると、欲しい回答を得られやすくなるため、ぜひ参考にしてみてください。
質問力を磨くメリット
仕事において重要な質問力を磨くメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、4つのメリットを紹介します。
目的やゴールを正しく理解できるようになる
質問力を使って目的やゴールを明確にしていくと、一緒に働く仲間もそれらを正しく認識し、動けるようになります。皆が目的やゴールを正しく理解することは、目標達成に近づくことであるため、良い結果を生みやすくなるでしょう。
人事、総務、法務など、数字の目標がない部署で働いている場合、皆が目的やゴールを読み違えて動くこともあり、共通認識がずれていると非効率な組織運営になりがちです。質問力を磨いて、効率良く働けるようにしていきましょう。
スムーズなコミュニケーション
目的やゴールを正しく理解できるようになると、皆の進むべき方向が明確になるため、その後は自然とスムーズなコミュニケーションがとれるようになります。質問することに慣れてくると、最初の時期に質問力を使って物事を明確にしておくことの重要性を感じられるでしょう。
情報収集ができる
仕事を進めていく上では、適切な情報収集が重要です。質問力を磨いていけば、「その仕事を進めるために重要な項目は何か、優先順位をどうつけるべきか」などを考える際にも、正しい情報がないと適切な判断ができません。
そうした事態に陥らず、正しい情報を収集できるだけでも質問力を磨くメリットはあります。
会話の誘導
仕事では相手と会話をしながら、自分の考える方向性に誘導しなければならないシーンもあります。その際に質問力があると、得たい回答を得られるような質問を選べるため、自然に会話を誘導できます。
メンバーマネジメントをする際、他部署との業務調整を行う際、取引先との交渉を行う際などあらゆる場面で使えるため、利便性が非常に高いです。会話を思った方向に誘導できると物事をスムーズに進められるので、質問力を備えておくメリットは大きいといえるでしょう。
質問力を磨くポイント

メリットの多い質問力を磨くにはどうしたらいいのか悩んでいる方に向けて、3つのポイントを紹介します。
仕事を進めた場合を想定し、浮かんできた質問を聞く
考えようにも何も質問が浮かんでこないという場合は、「もしこのままAという仕事を任されたら、あるいはこのまま仕事が進んだらどんなことが起こりそうか」を考えてみてください。
例えば「そもそもAという仕事について詳しく理解ができていない。基本知識はあるけれど、Bさんがやっていたこの方法を真似してやればいいのだろうか」という疑問が出てきたら「Aという仕事はBさんがこの方法でやっていたけれど、それを真似する方法で進めて問題ないでしょうか」と質問しましょう。
そうすれば少なくともBさんの方法でいいのか悪いのかは、わかります。その方法でいいなら「今回の仕事に取り組む際に気をつけるべきことがあれば教えてください」などと言えば、仕事のやり方と注意点を確認して取り組めますし、その方法ではいけないのであれば、新たにどういう方法でやるべきかを質問できます。
「そんな簡単な質問でいいのだろうか」と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、仕事を始める前にこうしたことを確認しておくのは非常に重要です。
物事の解像度を上げる質問を心がける
最初に目的やゴールなど、オープンクエスチョンで挙げたような質問をするのは難度が高いため、質問をすることに慣れるまでは、物事の解像度を上げるような質問を心がけることをおすすめします。
例えば、自ら不明な点を聞いて皆に理解を促すようにしたり、方向性を再確認したりなど、具体化することを心がけると、解像度を上げる質問ができるはずです。
・「◯◯だからやる必要があるのか」と皆が理解できるような背景を聞く
・「AではなくBということで合っていますか」と方向性を確認できる質問
・「具体的にやる場合は◯◯のような進め方になるでしょうか」と具体化する質問
否定ではなく建設的な質問を心がける
質問ができるようになってくると、「もっとこうしたらいいのに」「こういう観点が足りないのでは」などと感じるようになり、否定的な質問をし始める人もいます。
大前提、仕事は円滑に進めることが重要です。質問をして円滑に進んでいないようであれば、その質問は不要な可能性が高いといえるでしょう。迷った際は質問をする前に「この質問をして何が明確になるのか」「建設的に物事が運ぶようになるか」を自身に問いかけてみてください。
これら3つのポイントに気をつけた上で、この質問がふさわしいシーンか、質問の順番はこれでいいか、オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンの組み合わせはこれでいいかなどを確認する癖をつけるようにすると、質問力が磨かれていくはずです。
まとめ
仕事を円滑に、そして効率よく進めるために必要な質問力を磨くメリットと、身につけるやり方をあわせて紹介しました。
質問力を発揮できるほど磨かれていない、何から質問したらいいかわからないと感じている方は、ぜひこの記事で紹介した質問力を磨く方法を試してみてください。うまく質問ができると、仕事が一気に進む、コミュニケーションがうまくとれるなど、これまでと違う感覚を味わえるはずです。
仕事が楽しくなるよう、うまく進める鍵となる質問力の向上に取り組み、その変化を体感してみてください。
<ライタープロフィール>
高下 真美
新卒で人材派遣、人材紹介企業に入社し、人事・総務・営業・コーディネーターに従事。その後株式会社リクルートジョブズ(現・株式会社リクルート)に転職し、営業として8年勤務後、HR系ライターとしてフリーランスへ転身。現在は派遣・人材紹介・人事系メディアでの執筆、企業の採用ホームページの取材・執筆の他、企業の人事・営業コンサルタントとして活動中。