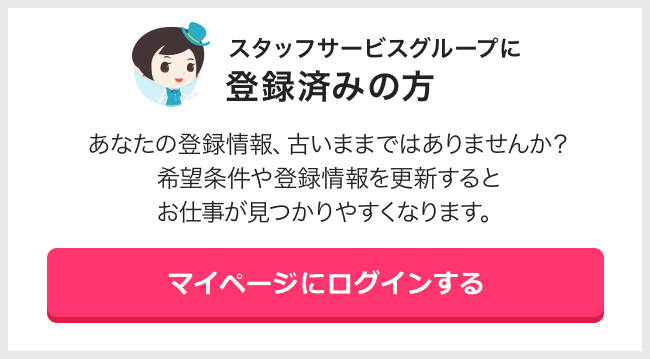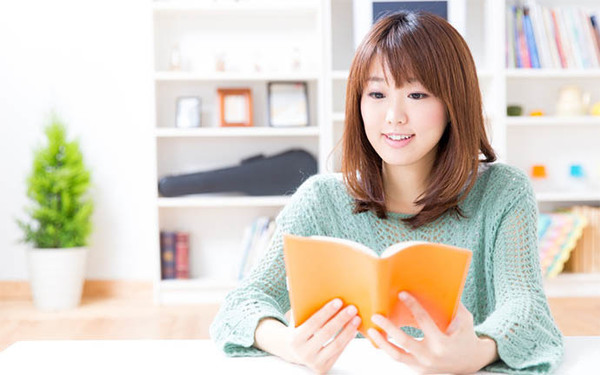派遣スタッフが社会保険に加入する条件とは?

社会保険とは広い意味で、健康保険や介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険(労災保険)をあわせたものです。派遣社員として働く場合も、条件を満たせば社会保険に加入できます。
一方で、名前は聞いたことがあるけれど「制度が複雑でよく分からない」「加入手続きはどうしたらいいのか」「保険料を引かれるのが嫌だから、扶養の範囲で働きたい」などと悩まれる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、社会保険の種類や加入条件、手続きの方法、扶養内で勤務する場合の注意点などをやさしく解説します。
目次
そもそも社会保険とは

社会保険制度とは、生活するうえで起こりうる病気やけが、老齢など、さまざまなリスクに備えるための公的な保険制度です。働きながら一定の保険料を納めることで、万が一のときには給付が行われ、社会全体で加入者を支える仕組みになっています。
企業などに雇われて働く人の社会保険には、次の5種類があります。
● 健康保険
● 介護保険
● 厚生年金保険
● 雇用保険
● 労働者災害補償保険
社会保険の概要
社会保険は正社員や派遣社員といった雇用形態に関係なく、条件を満たせば加入できます。
派遣社員の場合、実際に働く場所は派遣先企業ですが、保険に加入するのは派遣元企業になるのが特徴です。たとえば、「◯◯派遣会社」という派遣会社から派遣されて「△△商事」で働く場合は、「◯◯派遣会社」のもとで保険に加入することになります。
また、派遣元企業は自社の派遣スタッフを社会保険に加入させた場合、派遣先企業に対して「健康保険・厚生年金・雇用保険」の資格取得確認等を通知することが義務づけられています。もしも未加入の状態でスタッフを派遣する場合は、その理由も具体的に通知しなければなりません。
【参考】厚生労働省|平成21年度「労働者派遣事業雇用管理等援助事業」派遣相談事例集内のQ27参照
派遣社員の社会保険加入は義務?
派遣社員であっても、条件を満たす場合は社会保険加入の義務があります。「給料の手取り額が減ってしまうので社保に入りたくない」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、加入するかどうかを自由に選べるものではないので注意しましょう。
ただし、次の項目に該当する場合は社会保険加入の対象外となります。
● 雇用契約期間が2ヶ月以内の場合(※)
● 日雇いの場合
● 季節的な業務(4ヶ月以内)で働く場合
● 臨時的事業(6ヶ月以内)の事業所で働く場合
※契約期間が2ヶ月以内でも、それ以降も雇用される見込みがある場合は、最初から加入が必要です。
保険料が給与から引かれることで、「手取りが下がる」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、社会保険に加入することは「将来もらえる年金が増える」「産前産後休業で出産手当がもらえる(一定の条件あり)」などのメリットも多くあります。
【参考】日本年金機構 |適用事業所と被保険者
社会保険の種類と加入条件

ひとくちに「社会保険」と言っても、種類ごとに対象者や加入条件が異なります。①「健康保険」②「介護保険」③「厚生年金」④「雇用保険」⑤「労働者災害補償保険」の順に、各保険の概要と加入条件について詳しく解説します。
①健康保険
<健康保険>
目的:病気やけが、出産などの際に医療を受けるための保険
給付されるもの(抜粋):
● 療養の給付(医療機関で診察や薬の処方を受けたときの費用補助)
● 高額療養費(手術・入院などで医療費が高額になったときの費用補助)
● 傷病手当金(療養のため働けない期間の生活保障)
● 出産育児一時金・出産手当金(出産の費用や産休中の生活保障) など
【参考】 全国健康保険協会|保険給付の種類と内容
加入条件:健康保険の適用事業所で働く人のうち、以下に当てはまる人
常時雇用されているもの
短期労働者の場合、(1)(2)いずれかに該当するもの
(1)契約期間が2ヶ月以上で、1週間および1ヶ月の所定労働時間が正社員の4分の3以上の人
(2)次の5つの条件をすべて満たす人
● 週の所定労働時間が20時間以上
● 所定内賃金が月額8.8万円以上
● 雇用契約期間が2ヶ月以上を見込んでいる
● 学生ではない
● 従業員数が101人以上の企業(100人以下の場合も、労使で合意がなされていれば加入)(※)
(※)法改正により、2024年10月以降は「従業員数が51人以上の企業」になります。
【参考】厚生労働省|社会保険適用拡大ガイドブック
②介護保険
<介護保険>
目的:高齢者や一定の疾病で介護が必要な人を支えるための保険
給付されるもの(抜粋):
● 居宅サービス(訪問介護、訪問リハビリテーション)
● 施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設)
● 介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション)
加入条件:
40歳以上の健康保険加入者全員
介護保険の被保険者は、1号と2号に分かれています
● 第1号被保険者:65歳以上の人
● 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の人
健康保険の被保険者となっている40歳から64歳までの方は、介護保険料が健康保険料と一緒に給与から徴収されます。
【参考】厚生労働省|介護保険制度の概要
③厚生年金保険
<厚生年金保険>
目的:高齢者や障がい者、本人が亡くなったあとの遺族の生活を支えるための保険
給付されるもの(抜粋):
● 老齢厚生年金(老齢基礎年金に上乗せして支給される年金)
● 障害厚生年金(障がいがある場合に支給される年金)
● 遺族厚生年金(被保険者本人が亡くなったあと遺族が受け取れる年金)
加入条件:健康保険の加入条件と同様
【参考】厚生労働省|社会保険適用拡大ガイドブック
④雇用保険
目的:労働者の生活の安定のために失業や休業の際に給付をおこない、雇用の継続や就職の促進をはかる保険
給付されるもの(抜粋):
● 失業手当(労働者が失業し就職活動をしている間に支給される手当)
● 再就職手当(失業手当の受給資格がある方が再就職し一定の条件に該当した際に支給される手当)
● 教育訓練給付(一定の条件を満たす一般被保険者や被保険者でなくなってから1年以内の方が、指定された教育訓練を受講、修了した場合に支給される給付)
加入条件:次のいずれにも該当する労働者
(1) 週の所定労働時間が20時間以上である
(2) 31日以上の雇用の見込みがある
雇用保険の保険料は、事業主と労働者双方が負担します。労働者は、毎月の給与から天引きで徴収されるのが一般的です。保険料率は毎年見直しがおこなわれており、2024年3月現在の料率は以下となっています。
<雇用保険の保険料率(一般の事業の場合)>(2024年3月現在)
労働者が負担する金額…賃金の6/1000
事業主が負担する金額…賃金の9.5/1000
なお、2024年4月から2025年3月までの料率も上記と同様であることが発表されています。
【参考】厚生労働省|雇用保険の加入手続きはきちんとなされていますか
厚生労働省|令和6年度の雇用保険料率について
⑤労働者災害補償保険
目的:労働者の業務上または通勤中の事故やけが、病気、死亡などに対して、本人や遺族へ給付をおこなう保険
加入条件:労働者を1人でも雇っている事業所
労働者災害補償保険は、一般的に「労災保険」と呼ばれています。加入するのは労働者ではなく、企業側の義務です。このため、労災保険に加入する際に労働者側でおこなう手続きや必要書類は特にありません。
【参考】厚生労働省|労災補償
短期派遣の社会保険への加入条件
短期派遣の場合、契約期間やその後の更新見込みによって、加入できるかどうかが変わってきます。
前述の「短期労働者」の条件がそれにあたりますが、契約期間が2ヶ月以上の場合は、健康保険・厚生年金保険(40歳以上の人は介護保険)の加入義務が発生します。また、契約期間が2ヶ月未満であっても、その後も引き続き雇用される見込みがある場合は、最初から社会保険に加入しなければなりません。
派遣社員の社会保険の手続きについて

本章では、派遣社員の社会保険の具体的な手続きについて解説します。
加入や喪失の手続きは、基本的に派遣会社がおこないます。ここでは、一般的な手続きの流れや必要書類を紹介しますが、派遣会社によって異なる場合もあるため、詳しいことは勤務する派遣会社に確認しましょう。
派遣先企業で勤務開始するとき
派遣先企業や労働条件が決まったら、社会保険の加入手続きを行います。派遣会社に提出するものは、以下の3点です。
● マイナンバー
● 年金手帳
● 雇用保険被保険者番号
家族を扶養に入れる場合は、追加で以下の書類を求められることもあります。
● 住民票
● 家族のマイナンバー
● 配偶者の基礎年金番号
● 家族の収入証明書
加入手続きをしてから手元に健康保険証が届くまでには、早くて数日、遅ければ数週間の時間がかかります。通院の予定など、急ぎで必要な場合は派遣会社に事前に相談することをおすすめします。
派遣先企業を勤務終了するとき
派遣先企業での勤務を終了し、次の派遣先が決まっていない場合は、社会保険の喪失手続きをすることになります。速やかに、自分と扶養家族の健康保険証を派遣元会社に返却しましょう。
派遣会社での勤務終了後、国民健康保険に加入する予定の人は、「資格喪失証明書」という書類が必要になります。健康保険証を返却する際、派遣会社に発行を依頼しておくと手続きがスムーズです。
また、雇用保険を喪失すると「資格喪失確認通知書」や「離職票」が交付されます。ハローワークで失業保険を申請するときに必要になりますので、こちらも派遣会社に依頼しておきましょう。
派遣会社を変更するとき
現在の派遣会社を退社して別の派遣会社で就業する際には、改めて各種保険の加入手続きが必要です。前述の「派遣先企業で勤務開始するとき」と同様の手続きを、次の派遣会社でしてもらいましょう。
扶養内で勤務する場合の注意点

社会保険における扶養とは、自分自身で保険料を負担しなくても、加入している家族の保険に加入できる制度のことです。
扶養内で勤務する場合には、前述の社会保険の加入義務から除外されていることが前提です。たとえば、働き方の例として以下のようなものが考えられます。
● 所定内賃金が月額88,000円未満の範囲内で勤務する
● 2ヶ月未満の短期契約で勤務する
扶養内での勤務を希望する場合、年収が一定額を超えると扶養から外れてしまうため注意が必要です。あわせて、社会保険上の扶養の要件をおさえておきましょう。
<社会保険の扶養の要件>
年収が130万円未満(60歳以上または障がい者の場合は年収180万円未満)かつ
● 同居の場合:収入が扶養者の半分未満
● 別居の場合:収入が扶養者からの仕送り額未満
「フルタイムで働きたいけど、社会保険には入りたくない」という声も聞かれます。しかし、フルタイムの場合は、前述の社会保険の加入条件のとおり、労働時間や賃金の点からも配偶者の扶養から外れ、本人が社会保険に加入することが必須になります。
【参考】日本年金機構 |従業員が家族を被扶養者にするときの手続き
スタッフサービスでお仕事をしていただく際に加入する保険組合

最後に、スタッフサービスが加入する健康保険組合を紹介します。
今回紹介した保険のなかで、健康保険だけは保険組合や事業所登録をした都道府県ごとに保険料率や保険サービスが異なります。
スタッフサービスでは、どの会社に派遣される場合でも、最大の保険者である「全国健康保険協会(愛称:協会けんぽ)」の健康保険に加入していただきます。(※2019年4月~)
保険組合への加入に当たっては以下の用意が必要になります。
● 基礎年金番号、雇用保険被保険者番号
● マイナンバー
● 本人確認書類(免許証、パスポートなど)
● 住民票(世帯全員が記載されているもの)
まとめ
社会保険は、私たちの生活に起こりうる病気やけがといったリスクや、出産などライフイベントの際に補償を受けられる制度です。
給与から保険料が引かれることで、一見するとデメリットに注目がいきがちですが、マイナス面ばかりではありません。たとえば出産手当金は、扶養に入っている方(被扶養者)には支給されないなど、社会保険の被保険者ならではの手厚さも保障されています。ご自身やご家族のライフプランと照らし合わせて、長期的な視点で考えることをおすすめします。
- ライター:西本 結喜(監修兼ライター)
- 一般企業の人事職8年目。金融業界や製造業界を経験し、業界ごとの慣習や社風の違いを目の当たりにしてきた。現場で得た知識を深めたいと社会保険労務士試験に挑戦し、令和元年度合格。2024年3月社会保険労務士として独立。